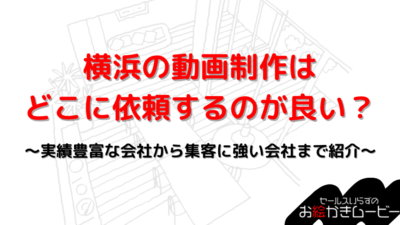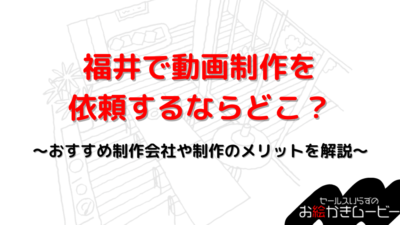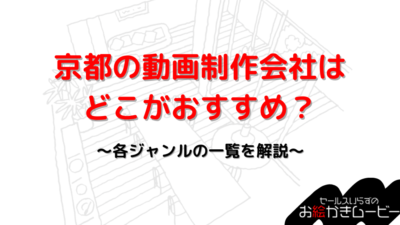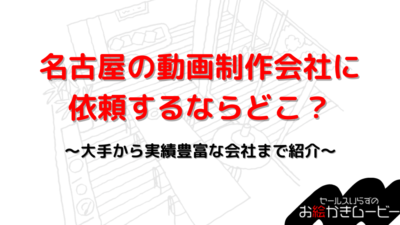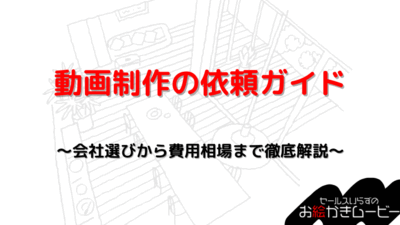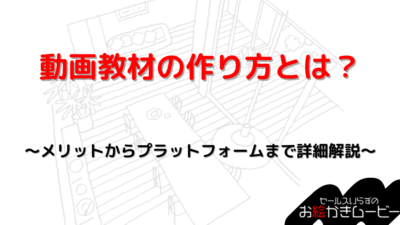採用動画の費用相場と料金は?成功事例から見る制作のコツも紹介!
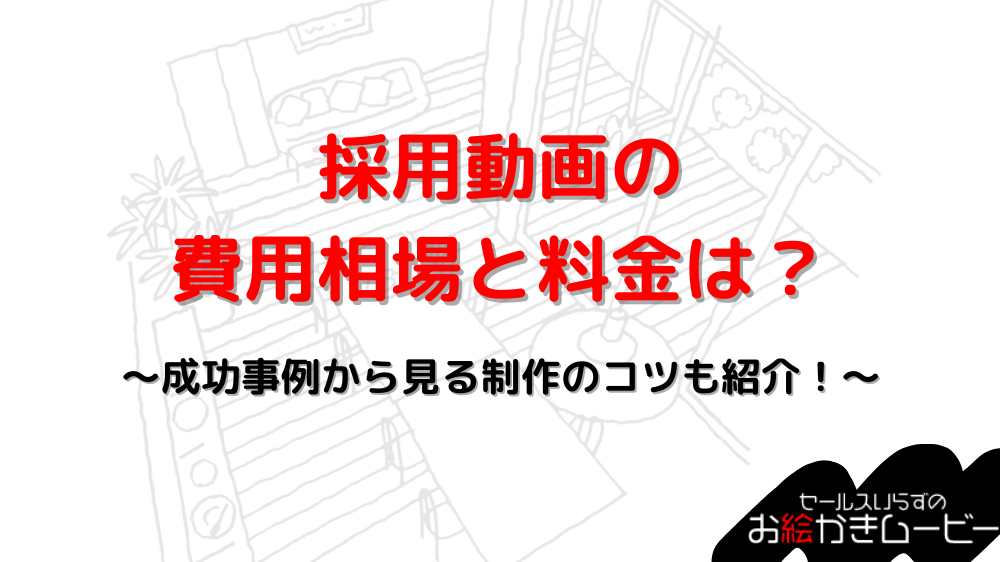
企業として新卒や中途の採用は、会社の業績を左右する一つの要素と言っても過言ではありません。
優秀な人材が来てくれなければ、教育などの費用もかさみ、会社の成長を阻害してしまう恐れがあります。
できるだけ優秀な人材に来てもらうためには、会社の良さをアピールする必要があるでしょう。
そのような中、必要とされているのが採用動画です。
しかしながら採用動画が必要となり、いざ制作しようにも以下のような不安や疑問を持っている人も少なくありません。
- 動画制作可能な担当者がいないので制作できないのでは?
- 外部に依頼しようにも費用が分からないため依頼しずらい
- 外部に依頼したら思ったより高額になってしまうのではないか?
そこで今回は採用動画の制作費用相場と料金や成功事例から見る制作のコツまで解説します。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/
なぜ採用動画は効果があるのか?導入する3つのメリット
採用競争が激化する今、採用動画は企業の未来を左右する重要な戦略ツールです。
テキストや静止画では伝えきれない企業のリアルな魅力を届け、求職者の心を動かします。
ここでは、採用動画がもたらす以下3つのメリットを詳しく解説します。
- ミスマッチ防止
- 認知度拡大
- 業務効率化
ここでしっかり採用動画のメリットを確認しておきましょう。
企業の魅力が伝わり、応募のミスマッチを防ぐ
動画は、テキストや写真に比べて圧倒的に多くの情報を伝えることができ、1分間の動画が持つ情報量は、文字に換算すると180万語に相当するとも言われています。
以下のようなリアルな情報は、求職者が企業の文化や価値観を直感的に理解する手助けとなります。
- 社員が働くオフィスの雰囲気
- 社員同士の何気ない会話や表情
- 経営者が語る事業への熱い想い
- 実際の仕事内容や一日の流れ
求職者は入社後の働き方を具体的にイメージできるため、「こんなはずじゃなかった」という入社後のギャップ、すなわちミスマッチを大幅に減らすことが可能です。
ミスマッチの防止は、早期離職率の低下に直結し、長期的に見れば企業の採用コスト削減に繋がります。
SNSでの拡散で潜在層にもアプローチできる
現代の求職者は、企業のSNSを重要な情報源としています。
動画コンテンツはSNSとの親和性が非常に高く、効果的な情報発信が可能です。
SNS媒体の種類とそれぞれの特徴や相性の良い動画は以下の表の通りです。
| SNS媒体 | 特徴と相性の良い動画 |
|---|---|
| YouTube | インタビューや会社説明会などの長尺で深い内容 |
| 企業の日常や雰囲気が伝わるショート動画(リール) | |
| TikTok | 若年層向けのエンタメ性が高いユニークな動画 |
| X (旧Twitter) | 短い動画でイベント告知や速報性のある情報を発信 |
これらのプラットフォームを適切に活用すれば、幅広い層へアプローチできます。
動画が魅力的であれば、「いいね」や「シェア」によってユーザーの手で自然に拡散されます。
これにより、今すぐの転職を考えていない「潜在層」にも企業の存在を届け、未来の応募者候補を育てるブランディング効果が期待できるのです。
採用活動のDX化と担当者の負担軽減
採用担当者の業務は、説明会の開催から面接、応募者管理まで多岐にわたります。
採用動画は、これらの業務を効率化し、担当者の負担を大幅に軽減する採用DXの切り札です。
以下の業務を動画に置き換えることで、時間と場所の制約なく情報を提供できます。
- 会社説明会での企業概要説明
- 応募者への一次的な情報提供
- 内定者向けの研修やオリエンテーションの一部
一度制作すれば、動画は「24時間365日」繰り返し企業の魅力を伝え続けてくれるツールになります。
説明会で何度も同じ説明をする手間が省け、担当者は本来注力すべき面接や応募者とのコミュニケーションといった、人でなければできないコア業務に集中できるようになるでしょう。
【料金表】採用動画の依頼先別の特徴・費用相場と種類
採用動画の依頼先は、主に以下の3つです。
- 制作会社
- フリーランス
- 内製
それぞれに費用感や特徴が大きく異なります。
ここでは、各依頼先の費用相場や特徴、動画種類別の費用感の違いを解説します。
動画制作会社:費用目安 20万~200万円以上
動画制作会社は、企画から撮影、編集までをワンストップで請け負う専門家集団です。
特徴は以下の表の通りです。
- 高いクオリティが期待できるが費用が高額になりやすい
- 企画から丸投げできる
- 担当者の負担が少ない
- 制作会社によって得意分野が違う
- コミュニケーションコストがかかる場合がある
これらの特徴から、安定した品質と手厚いサポートを求める企業に適しています。
特に、企業のブランドイメージを左右する重要な動画や、テレビCMレベルのクオリティを求める場合には最適な選択肢です。
複数の制作会社から見積もりを取り、実績や担当者との相性を比較検討することが成功の鍵となります。
フリーランス(個人):費用目安 5万~30万円
フリーランスは、個人で動画制作を請け負うクリエイターです。
特定のスキルに特化している場合が多く、柔軟な対応が期待できます。
特徴は以下の通りです。
- 制作会社より費用を抑えられる
- 直接クリエイターとやり取りできるため、意思疎通がスムーズ
- 得意分野が明確で、特定の作風を求める場合に適している
- 個人のスキルに依存するため、品質にばらつきがある
- 対応できる業務範囲が限られる場合がある
これらの特性を理解し、上手く活用することが重要です。
コストを抑えつつ、WebサイトやSNSで使う動画を制作したい場合に適しています。
依頼する際は、ポートフォリオ(過去の実績)を必ず確認し、作りたい動画のイメージとクリエイターの作風が合っているかを見極めましょう。
内製(自社制作):費用目安 0~10万円
内製は、自社の社員が企画から編集までを行う方法です。
特徴は以下の通りとなります。
- 費用を最も安く抑えられるが高いクオリティを出すのが難しい
- スケジュール調整がしやすいが制作に時間と手間がかかる
- 企業の理念や想いを反映させやすい
- 専門的な機材やソフトが必要になる
これらの特徴から、コストを最優先し、社内にリソースがある場合に有効な手段です。
採用サイトで流す社員インタビューや、簡単なSNS投稿用の動画など、速報性や手軽さが求められるコンテンツ制作に向いています。
近年は高機能な動画編集アプリも多いため、まずは簡単な動画から挑戦してみるのも良いでしょう。
【動画の種類別】費用感の違いを理解する
採用動画は、その表現方法によって制作の工数が異なり、費用も大きく変動します。
代表的な種類と費用感の目安は以下の通りです。
| 動画の種類 | 費用の傾向 | 特徴 |
|---|---|---|
| インタビュー動画 | 低~中 | 構成がシンプルで費用を抑えやすい |
| 会社紹介動画 | 中 | 撮影箇所が多く、標準的な費用 |
| ドラマ風動画 | 高 | 企画や複数日の撮影が必要で高額に |
| アニメーション動画 | 高 | 専門スキルが必要で高額になりやすい |
これらは、動画の目的と伝えたいメッセージに応じて使い分けるのが重要です。
一般的に、企画が複雑で撮影や編集に多くの手間がかかる動画ほど費用は高くなります。
自社の予算と採用ターゲットに合わせて、最も費用対効果の高い動画の種類を選びましょう。
会社紹介動画の費用を決める5つの要素【内訳】
動画制作の見積もりは、様々な要素で構成されています。
内訳を理解すれば、価格の妥当性を判断でき、費用交渉にも役立ちます。
費用を決める主な要素は以下の5つです。
- 企画構成費
- 人件費
- 機材・スタジオ費
- BGM・素材費
- 諸経費
ここでは上記要素について、それぞれ詳しく解説していきます。
企画構成費(シナリオ・絵コンテ作成など)
企画構成費は、動画制作の土台となる「設計図」を作るための費用です。
具体的に行う内容は以下の通りです。
- 目的やターゲットのヒアリング
- メッセージやコンセプトの設計
- シナリオ(脚本)の作成
- 絵コンテや字コンテの作成
動画のクオリティを左右する最も重要な工程と言っても過言ではありません。
上記に記載した項目などの緻密な準備が、伝えたいメッセージを的確に表現する動画の基盤を築きます。
この工程を自社で担当すれば費用を抑えられますが、プロに任せることで、より訴求力の高い構成が期待できます。
ここでの投資は、撮影後の手戻りを防ぎ、最終的な動画のクオリティを保証する上で不可欠な要素です。
人件費(ディレクター、カメラマン、編集者など)
人件費は、動画制作に関わる専門スタッフの稼働に対する費用で、制作費の大部分を占める要素です。
制作スタッフの主な役割は以下の通りです。
- ディレクター:制作全体の指揮・監督
- カメラマン:映像の撮影
- 音声スタッフ:録音
- 照明スタッフ:光の調整
- 動画編集者:カット編集、テロップ、エフェクト追加
これらの専門家が関わることで、映像の品質が飛躍的に向上します。
制作の規模が大きくなるほど関わる人数が増え、人件費も高くなります。
一方で、撮影から編集まで一人でこなすフリーランスに依頼する場合、人件費を抑えることが可能です。
クオリティと予算に応じて、最適なチーム編成を検討しましょう。
撮影機材・スタジオ費
プロ品質の映像を撮影するためには、専門的な機材や撮影場所が必要です。
費用の種類と具体例は以下の表の通りです。
| 費用の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 機材費 | 高性能カメラ、レンズ、マイク、照明、三脚など |
| スタジオ費 | 白ホリスタジオ、ハウススタジオ、クロマキースタジオなど |
| 美術費 | 撮影で使う小道具や背景セットなど |
これらの要素は、動画の世界観を構築し、視聴者への訴求力を高めます。
自社のオフィスで撮影すればスタジオ費はかかりませんが、理想の映像を追求するならスタジオ利用が効果的です。
使用する機材のグレードやスタジオの規模によって費用は変動するため、企画内容に合わせた選択が求められます。
BGM・ナレーション・素材費
映像の魅力を引き立てる音や視覚素材にも費用がかかります。
詳細は以下の通りです。
- BGM:動画の雰囲気を演出し、感情に訴えかける
- ナレーション:情報を分かりやすく伝え、信頼性を高める
- 画像・動画素材:実写では表現しきれない部分を補う
これらの聴覚・視覚情報が、動画の完成度を大きく左右します。
BGMや素材には、無料のものから高価な有料のものまで様々です。
プロのナレーターに依頼すれば数万円からの費用が発生します。
企業のブランドイメージに合った素材を選びましょう。
ただし、素材選びの際には、今後のトラブルにならないよう、著作権をクリアした音源・素材を使用してください。
諸経費(交通費、ロケハン費など)
諸経費は、動画制作のプロジェクトを円滑に進めるために発生する、上記以外の様々な費用を指します。
具体的なものは以下の通りです。
- 交通費・宿泊費:遠方での撮影やスタッフの移動にかかる費用
- ロケハン費:撮影場所の下見にかかる費用
- 車両費:撮影機材の運搬に必要な車両のレンタル費用
- スタジオ予約費:撮影スタジオの確保にかかる費用
これらの費用は、撮影の規模や場所によって大きく変動します。
見積もりを取る際は、これらの諸経費がどこまで含まれているのかを必ず確認しましょう。
特に遠方での撮影を希望する場合は、交通費や宿泊費が高額になる可能性があるため、事前の確認がトラブル防止に繋がります。
費用を抑えつつ効果的な採用動画を作るコツ
採用動画は効果的ですが、制作費用が課題になる場合があります。
しかし、ただ費用を削っては魅力が伝わりません。
ここでは、効果を損なわずに制作コストを賢く抑えるための4つのコツを紹介します。
企画や構成案を自社で固めておく
動画制作費の中でも大きな割合を占めるのが「企画構成費」です。
この工程を自社で進めておけば、費用を大幅に削減できます。
- 動画の目的(誰に何を伝えたいか)
- 伝えたいメッセージの優先順位
- 大まかなストーリーの流れ
上記の骨子を事前に固めておくだけで、進行が非常にスムーズになります。
制作会社はゼロから企画を練る工数が減り、その分費用を抑えることできるでしょう。
明確な企画は手戻りを防ぎ、全体のコストダウンに繋がる最も効果的な方法です。
社員に出演してもらう
プロの俳優やモデルの起用には高額な出演料がかかります。
そこで最も効果的なのが、以下のメリットが得られる自社の社員に出演してもらう方法です。
- 出演料やキャスティング費用を削減できる
- 社員の言葉でリアルな声が届けられる
- 企業の「人」の魅力が伝わり親近感が湧く
コスト削減と同時に、動画の訴求力を高める効果が期待できます。
プロではない社員のありのままの姿は、企業のリアルを映し出します。
その飾らない姿が求職者の共感を呼び、信頼関係を築く上で何よりの強みとなるのです。
撮影場所を自社オフィスにする
レンタルスタジオの利用には数万円以上の費用がかかります。
この費用を抑える最も簡単な方法は、撮影場所を自社のオフィスにすることです。
撮影場所を自社オフィスにすると得られるメリットは以下の通りです。
- スタジオのレンタル費用が不要になる
- 実際の職場環境をリアルに見せられる
- 社員がリラックスして撮影に臨みやすい
費用削減と同時に、求職者へのアピール効果も期待できます。
求職者が知りたい情報の一つが「実際に働く環境」です。
普段のオフィスで撮影すれば、入社後の働き方を具体的にイメージしてもらえます。
オフィスの雰囲気を伝える方法は、ミスマッチ防止にも繋がる賢い選択になるでしょう。
テンプレートや補助金を活用する
ゼロから作る以外にも、費用を抑える方法はあります。
特に有効なのが、動画制作テンプレートや、国・自治体の補助金の活用です。
以下表のような外部リソースを上手く活用できると、制作の負担を軽減できます。
| 活用方法 | 特徴 |
|---|---|
| 動画制作テンプレート | 安価な料金で、プロ品質のフォーマットを利用できる |
| 補助金・助成金 | 採用力強化などを目的とした公的支援(返済不要な場合も) |
テンプレートを使えば数万円から制作が可能ですし、補助金が採択されれば費用の半分以上が補助されることもあります。
「〇〇(地域名) 採用 補助金」などで検索し、動画制作の補助金について、自社で活用できる制度がないか調べてみると良いでしょう。
これが最新!採用動画のトレンドと成功事例
求職者の心を掴むには、最新トレンドの理解と成功事例からの学びが不可欠です。
ここでは、現在注目されている3つの動画トレンドを解説するとともに、大手・中小企業の具体的な成功事例を紹介します。
自社に合った効果的な採用動画を作るためのヒントが、きっと見つかるはずです。
トレンド1:社員のリアルを伝える「Vlog風動画」
Vlog(ブイログ)風動画とは、社員の1日に密着し、その日常業務や働き方をリアルに映し出すスタイルの動画です。
作り込まれた映像とは異なり、ありのままの姿を見せることで、求職者に強い親近感と信頼感を与えます。
以下のような飾らない日常風景が、求職者にとって最も知りたい情報となります。
- 出社から退社までの1日の流れ
- ランチや休憩時間の過ごし方
- チームメンバーとの会議や雑談の様子
- リモートワークの日の働き方
従来の会社説明では伝わりにくい「社風」や「人」の魅力を直感的に伝えることができるため、入社後のイメージギャップを減らし、ミスマッチ防止に絶大な効果を発揮します。
authentic(本物)であることが、現代の求職者の心を動かす鍵です。
トレンド2:共感を呼ぶ「ドキュメンタリー動画」
ドキュメンタリー動画は、特定のプロジェクトや一人の社員の挑戦、企業の歴史などに焦点を当て、ストーリー性豊かに描く手法です。
単なる紹介ではなく、視聴者の感情に訴えかけ、深い共感を呼び起こします。
以下のような物語を通じて、視聴者は企業の価値観を深く理解することができます。
| ドキュメンタリーのテーマ例 | 伝えられるメッセージ |
|---|---|
| 新商品開発プロジェクト | 仕事のやりがい、チームワーク |
| 若手社員の成長ストーリー | 企業の育成文化、キャリアパス |
| 創業時の苦労と理念 | 企業のDNA、社会的存在意義 |
情報を伝えるだけでなく、登場人物の葛藤や成功体験を共有することで、視聴者は企業を「応援したい」と感じるようになります。
企業の理念やビジョン、仕事への情熱といった、目に見えない価値を伝えるのに非常に効果的なトレンドです。
トレンド3:Z世代に響く「ショート動画」
TikTokやInstagramリールに代表されるショート動画は、特にZ世代へのアプローチに不可欠なツールです。
短い時間で気軽に視聴できるため、企業の認知度を広げる「入口」として絶大な効果を発揮します。
以下のキャッチーなコンテンツは、求職者の興味を引くきっかけとなります。
- 1分でわかるオフィスツアー
- 社員への一問一答チャレンジ
- 面白おかしく紹介する仕事内容
- 説明会やイベントの告知
ショート動画の最大の強みは、その視聴ハードルの低さとSNSでの拡散力です。
まだ転職を考えていない潜在層にも企業の存在を知らせることができ、採用活動の裾野を大きく広げます。
まずはショート動画で興味を持ってもらい、YouTubeの長尺動画や採用サイトへ誘導する、という戦略も非常に有効です。
【事例】大手企業と中小企業の成功ポイント
採用動画の戦略は、企業の規模や予算によって異なります。
大手企業と中小企業の成功事例から、それぞれのポイントを学びましょう。
| 企業規模 | 戦略・成功ポイント |
|---|---|
| 大手企業 | ・豊富な予算で高品質な映像を制作する ・ブランドイメージの向上を強く意識する ・企業の歴史やビジョンを壮大に伝える ・社員の多様性を見せて安心感を醸成する |
| 中小企業 | ・アイデアと工夫で大手企業と差別化する ・座談会や密着動画でリアルな社風を見せる ・社員一人ひとりの「人柄」を前面に押し出す ・大手にはない親近感や一体感をアピールする |
これらの事例は、自社の強みを最大限に活かす方法を示唆しています。
規模に関わらず共通する成功の鍵は、ターゲットを明確にし、社員のリアルな声を届けることです。
採用動画の事例も見ていきましょう。
上記は、ソニーミュージックグループ新卒採用2016オープニングムービーです。
音楽を軸とした多様な事業をスタイリッシュな映像で表現され、企業の先進的なブランドイメージを伝えています。
上記は【日本住宅ローン】新卒採用動画「新卒社員座談会」の様子です。
新卒社員による座談会形式となっています。
リアルな会話を通して、風通しの良い職場の雰囲気や社員の人柄を伝えています。
求職者に響く採用動画の作り方【構成・活用法】
効果的な採用動画を作成するためには、適切な構成が欠かせません。
ここでは、採用動画の基本的な構成、効果的な構成事例、そして構成における注意点について解説します。
動画制作で失敗しないための基本構成
採用動画でメッセージを効果的に伝えるには、ストーリーの「型」となる構成が重要です。
行き当たりばったりで作るのではなく、視聴者の感情の流れを意識した構成を考えましょう。
代表的な基本構成は以下の通りです。
| 構成ステップ | 内容 | 役割 |
|---|---|---|
| 掴み(冒頭5秒) | 最も伝えたいメッセージや印象的な映像 | 視聴者の興味を引き、離脱を防ぐ |
| 共感・課題提起 | 求職者の悩みや企業の課題を提示 | 「自分ごと」として捉えてもらう |
| 解決策・企業の魅力 | 企業の理念や働き方が解決策となることを示す | 企業の価値を具体的にアピールする |
| 未来・行動喚起 | 入社後の未来像を見せ、次のアクションを促す | 応募へのモチベーションを高める |
この流れを意識することで、伝えたいメッセージに一貫性が生まれます。
この構成はあくまで基本形ですが、これを意識するだけで動画の内容が格段に整理され、求職者に響くストーリーを作りやすくなります。
まずはこの型に沿って、自社の伝えたいことを当てはめてみることから始めましょう。
効果的な採用動画の構成事例
採用動画は、一度制作すれば様々な場面で活用できる強力な資産です。
以下のように採用活動の各フェーズで戦略的に活用すると、その効果を最大限に引き出せます。
- 会社説明会や合同企業説明会での上映
- 採用サイトや求人媒体への掲載
- スカウトメールや応募者への案内メールへの添付
- 内定者向けのフォローアップコンテンツ
- 大学などでのキャリアガイダンス
これらのシーンで動画を活用することで、一貫したメッセージを届けることが可能です。
例えば、説明会では全体の雰囲気を伝える動画を、選考段階ではより深い仕事内容を伝える動画を見せるなど、フェーズに合わせて使い分けるのが効果的です。
これにより、求職者の企業理解と志望度を段階的に高めていけるでしょう。
採用サイトやSNSでの効果的な見せ方
採用サイトやSNSで動画を公開する際は、ただアップロードするだけでなく「見せ方」を工夫しましょう。
各媒体における、効果的な見せ方のコツは以下表の通りです。
| 媒体 | 効果的な見せ方のコツ |
|---|---|
| 採用サイト | トップページなど目立つ位置に配置し、 autoplay(自動再生)設定にする |
| YouTube | 魅力的なサムネイル画像を設定し、タイトルにキーワードを入れる |
| SNS (X, Insta) | 冒頭で惹きつけ、無音再生でも伝わるよう字幕を必ず入れる |
これらの工夫一つで、動画がクリックされる確率が大きく変わります。
特に、動画の「顔」となるサムネイルは非常に重要です。
求職者が思わずクリックしたくなるような、魅力的で内容が伝わる画像を設定しましょう。
各プラットフォームのユーザー層や特性を理解し、それぞれに最適化した「見せ方」を追求できると、採用動画の効果が高まります。
失敗しない採用動画の制作会社の選び方
採用動画の成功は、依頼先選びで決まります。
「費用が安い」だけで選ぶと失敗の原因になりかねません。
ここでは、自社に最適なパートナーを見極めるための、重要な3つの選定ポイントを解説します。
作りたい動画ジャンルの実績が豊富か
依頼先を選ぶ際、まず初めに確認すべきなのが過去の実績(ポートフォリオ)です。
その制作会社やフリーランスがどのような動画を作ってきたのかが分かれば、スキルのレベルや作風を判断できます。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 作りたい動画のジャンル(採用、商品紹介など)の実績が豊富にあるか
- 映像のクオリティ(画質、音質、編集)は十分か
- 自社のブランドイメージやテイストと合っているか
これらの視点で実績を確認できれば、完成後のイメージのズレを防げます。
自社が作りたい動画のイメージに近い実績が豊富にある依頼先を選び、成功に繋げていってください。
担当者とのコミュニケーションはスムーズか
動画制作は、依頼側と制作側が密に連携して進める共同作業です。
そのため、担当者とのコミュニケーションがスムーズに行えるかどうかは、制作の進行と動画のクオリティに直結します。
良い担当者と注意すべき担当者の特徴は以下の表の通りです。
| 良い担当者の特徴 | 注意すべき担当者の特徴 |
|---|---|
| ・レスポンスが迅速で丁寧 ・専門用語を分かりやすく説明してくれる ・こちらの要望を丁寧にヒアリングしてくれる | ・返信が遅い、または無い ・専門用語ばかりで話が分かりにくい ・意見を聞かず、提案を押し付けてくる |
これらのポイントは、プロジェクトを円滑に進めるための重要な指標となります。
どんなに実績が素晴らしくても、担当者との意思疎通がうまくいかなければ、要望が正しく伝わらず、満足のいく動画は作れません。
問い合わせや初回の打ち合わせの段階で、親身に対応してくれるか、信頼できるパートナーとなり得るかしっかりと見極めましょう。
見積もりの内訳が明確で丁寧か
複数の依頼先候補が見つかったら、必ず相見積もり(複数の会社・個人からの見積もり)を取りましょう。
その際、単に総額の安さだけで比較するのではなく、見積もりの内容が明確で丁寧かどうかを精査することが重要です。
見積もり時には、以下のポイントを必ずチェックしましょう。
- 各工程(企画、撮影、編集など)の費用が記載されているか
- 「一式」などの不明瞭な項目が多すぎないか
- 修正回数の上限や、追加料金が発生する条件が明記されているか
- BGMやナレーションなどの費用が含まれているか
これらの項目が詳細に記載されている見積もりは、信頼性が高いと言えます。
逆に、内訳が不明瞭な見積もりを提示する会社は、後から高額な追加料金を請求してくる可能性があるので注意が必要です。
誠実な会社は、顧客が納得できるよう丁寧な見積もりを作成してくれます。
後のトラブルを避けるためにも、不明点は契約前に必ず確認しましょう。
よくある質問
最後によくある質問について解説しますので、確認していきましょう。
採用動画の制作期間はどれくらいですか?
用動画の制作期間は、企画開始から納品まで、一般的に1.5ヶ月〜3ヶ月程度が目安です。ただし、この期間は動画の内容によって大きく変動します。
- 動画の種類や長さ(インタビューかドラマ風か)
- 企画や構成の複雑さ ・撮影の規模(日数、場所)
- 依頼主側の確認やフィードバックの速さ
これらの要素が、全体のスケジュールに影響を与えます。
特に、企画のすり合わせや修正に時間がかかることが多いため、希望の公開時期がある場合は、余裕を持ったスケジュールで依頼しましょう。
契約前に制作会社と詳細なスケジュールを共有し、合意しておくのが重要です。
採用動画の効果測定はどのように行いますか?
採用動画の効果測定は「定量的」と「定性的」の両面から行います。
まず動画公開前に「応募者数を20%増やす」などの目標(KPI)を設定してください。
測定指標の例は以下表の通りです。
| 定量的な測定指標 | 内容 |
|---|---|
| 再生回数・維持率 | 動画への関心度 |
| クリック率(CTR) | 採用サイトへの誘導率 |
| 応募数・内定承諾率 | 実際の採用成果への貢献度 |
これらの数値データで、動画のパフォーマンスを客観的に評価します。
加えて、面接や内定者アンケートで「動画のどの部分が印象に残りましたか?」と質問し、定性的な評価を集めても良いでしょう。
これらのデータを分析のうえ、次の採用戦略に活かし、動画をブラッシュアップしていってください。
費用が安い制作会社に依頼しても大丈夫ですか?
費用が安い制作会社が一概に悪いとは言えませんが、安さの理由を理解し、慎重に判断する必要があります。
価格だけで選ぶと、以下のような失敗に繋がる可能性があります。
- テンプレート的で、企業の魅力が伝わらない
- 修正対応に別途高額な費用がかかる
- 実績が乏しく、クオリティが低い
これらのリスクを避けるためにも、安さの理由を必ず確認してください。
例えば、特定のジャンルに特化していて効率化を図っている、小規模なチームで固定費が少ないなどの理由であれば安心できます。
総額だけでなく、実績や担当者の対応、見積もりの内訳などを総合的に見て、信頼できるパートナーか見極めましょう。
まとめ
本記事では、採用動画の費用や、採用動画の成功事例、トレンドまで活用方法を解説しました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 採用動画には求職者とのミスマッチを防げるなど様々なメリットがある
- 制作の費用相場は依頼先や内容によって異なる
- 採用動画のトレンドには「Vlog風動画」や「ドキュメンタリー風の動画」などが存在する
- 視聴者の感情の流れを意識した採用動画の構成やSNSなどを使うのが効果的
採用動画は、求職者に対して企業に関心を向けてもらうための大事な要素の一つです。
それだけに、目的とターゲットに合わせた動画制作が求められます。
採用動画の制作を始めようと考えたら、まずは外注にするか内製にするか検討するところから始めてみてはいかがでしょうか?
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/