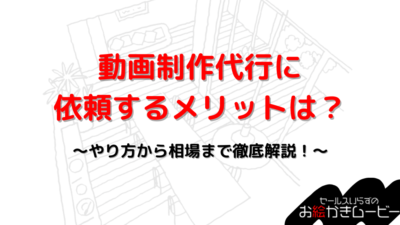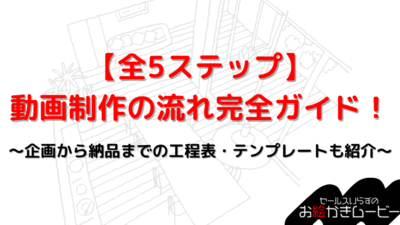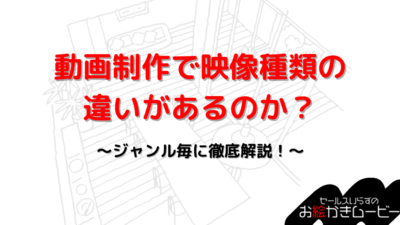最新版!SNS動画の作り方!インスタ等の最適な長さ・費用も解説!

企業のマーケティングにおいて、SNS動画の活用は売上を大きく左右する重要な鍵となっています。
若者を中心に多くのユーザーが集まるSNSで魅力的な動画を発信できれば、商品の認知拡大やファンの獲得に繋がる大きなチャンスが眠っています。
しかし、いざSNS動画を活用しようとしても、以下のような疑問や不安があることでしょう。
- 「そもそも、どんな動画が成果に繋がるの?」
- 「各SNSの特性に合わせた動画の作り方がわからない」
- 「動画制作や広告運用にかかる費用はどれくらい?」
この記事では、企業のSNS担当者が本当に知りたい情報を徹底的に解説します。
InstagramやTikTok、X(旧Twitter)など、各SNSで成果を出すための動画の作り方から、具体的な制作費用や広告費用の相場までを網羅的に紹介します。
この記事を読めば、SNS動画活用の「わからない」が解消され、明日から何をすべきかが見えてくるはずです。
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品や自社サービスをさらに販売できる!/
なぜ今、SNSで動画活用が重要なのか?3つの理由
テキストや静止画だけでなく、「動画」をSNSで活用することが、企業のマーケティング活動において欠かせない要素となっています。
その理由は、動画が持つ「情報伝達力」「ユーザーの興味を引く力」「拡散力」にあります。
ここでは、SNSで動画を活用すべき3つの理由を簡潔に解説します。
テキストの5000倍!圧倒的な情報伝達力
動画は、テキストの5000倍の情報量を持つと言われています。
映像、音声、テロップ(文字)を組み合わせることで、静止画や文章だけでは伝えきれない商品・サービスの魅力やブランドの世界観を、短時間で直感的に伝えることが可能です。
複雑な使用方法や、目に見えないサービスの価値も、動画ならユーザーに分かりやすく届けられます。
ユーザーの目を引き付け、滞在時間を延ばす効果
テキストや静止画が並ぶSNSのフィード上で、動きのある動画はユーザーの視線を自然と引きつけ、「スクロールする指を止める」力が非常に強いのが特徴です。
ユーザーの興味を引いてコンテンツへの滞在時間を延ばすことは、結果としてプラットフォームからのアカウント評価を高めることにも繋がります。
まずはユーザーの目に留めてもらう、というSNSマーケティングの第一歩において、動画は極めて有効な手段です。
「いいね」や「シェア」を促し、拡散されやすい
動画は、音楽やストーリー性を通じてユーザーの感情を動かしやすいフォーマットです。
「面白い」「感動した」「役に立った」といった感情は、「いいね」「コメント」「保存」そして「シェア」といった行動を強く促します。
特に、ユーザーによるシェアは広告費をかけずに情報を届ける強力な口コミとなり、爆発的な認知拡大を生む可能性があります。
このエンゲージメントの高さと拡散力の強さこそ、SNSで動画を活用する最大のメリットの一つと言えるでしょう。
【目的別】主要SNSプラットフォームと動画の特徴
SNSで動画を活用する際は、各プラットフォームのユーザー層や文化を理解し、目的に合わせた使い分けが成功の鍵を握ります。
ここでは「認知拡大」「ファン育成」といった目的別に、主要SNSの動画活用のポイントを解説します。
①Instagram|世界観の醸成とファンとの交流に最適
Instagramは、ビジュアルによる表現力が高く、ブランドの世界観を伝えながらファンとの関係を深めるのに最適なSNSです。
以下の複数の動画フォーマットを使い分ける戦略が求められます。
- リール:トレンドの音楽や編集で、新規フォロワーへリーチ(認知拡大)
- ストーリーズ:日常的な裏側やアンケート機能で、既存ファンとの交流を深化(ファン育成)
- フィード:作り込んだ動画で、ブランドイメージや世界観を構築(ブランディング)
- インスタライブ:リアルタイム配信で、商品の魅力を伝えながら質問に回答(販売促進)
これらを組み合わせ、ユーザーを飽きさせない多角的なアプローチが有効です。
②TikTok|若年層へのリーチとトレンド創出の起爆剤
TikTokはトレンドに敏感な若年層が多く、エンターテイメント性の高い動画が爆発的に拡散される可能性があります。
短期的な認知拡大に絶大な効果を発揮します。
活用ポイントは以下の表の通りです。
| 目的 | アプローチ |
|---|---|
| 認知拡大 | 流行の音源やエフェクトを使った「面白い」「真似したい」動画を投稿 |
| 話題化 | ハッシュタグチャレンジなどを企画し、ユーザー参加型のコンテンツを展開 |
広告感が強いコンテンツは敬遠されやすいため、ユーザー目線で楽しめるクリエイティブが重要です。
③YouTube|長尺での情報提供とファンコミュニティ形成
YouTubeは、長尺で詳細な情報提供ができ、検索にも強いため、動画コンテンツが企業の「資産」として蓄積されます。
専門性や信頼性を示し、じっくりとファンを育成するのに向いています。
YouTube動画の代表例は以下の通りです。
- 商品の詳しい使い方を紹介するHow-to動画
- 開発秘話やお客様の声といったストーリー動画
- 専門知識を分かりやすく解説する教育系動画
作成した動画は、継続的に見込み顧客を呼び込む重要な窓口になります。
④X(旧Twitter)|リアルタイム性と高い拡散力が魅力
X(旧Twitter)は、情報の即時性と拡散力が最大の武器です。
世の中のトレンドや「今」起きている話題と自社を結びつけた、スピード感のある動画コミュニケーションに適しています。
X(旧Twitter)活用の具体例としては以下の通りです。
- 新商品やキャンペーンの即時告知
- ユーザーの投稿(UGC)への反応や感謝を動画で伝える
- 社会的な話題に合わせた素早い情報発信
短い動画でもタイムライン上で効果的に注目を集め、ユーザーとの会話を生み出すフットワークの軽さが鍵です。
⑤Facebook|高精度なターゲティングと幅広い年齢層へ訴求
Facebookは、実名登録制のため、比較的フォーマルで信頼性の高い情報発信に向いています。
企業の取り組みを伝えたり、ビジネス層や高めの年齢層へアプローチしたりする際に効果的です。
Facebookでの動画活用例は以下の通りです。
- 企業の理念や社会貢献活動に関する動画
- イベントレポートやお客様インタビュー
- Facebookグループを活用した限定動画の配信
特にBtoB企業や、地域に根差したビジネスで顧客との信頼関係を築きたい場合に有効な選択肢となります。
成果を出すSNS動画の作り方 5つのポイント
SNSで動画をただ投稿するだけでは、期待する成果を得るのは困難です。
ユーザーの指は常に次のコンテンツへと動く準備ができており、無数の動画が流れるタイムラインの中で一瞬で興味を引く必要があります。
ここでは、企業のSNS担当者が押さえておくべき、成果に直結する動画作りの5つの重要なポイントを、具体的なテクニックと共に解説します。
これらのポイントを意識するだけで、あなたの動画は劇的に変わるはずです。
ポイント1:最初の1~3秒で心を掴む「冒頭の仕掛け」
SNS動画において、最も重要なのが「冒頭の1~3秒」です。
ユーザーはこのわずかな時間で、動画を視聴し続けるか、あるいは無慈悲にスワイプして次の動画へ移るかを判断します。
ここで視聴者の心を掴み、「自分に関係がある」「この先が気になる」と思わせる仕掛けが不可欠です。
具体的には、以下のようなテクニックが有効です。
- 視聴者の悩みに共感する問いかけ(例:「その毛穴悩み、まだ放置する?」)
- 最も伝えたい結論やメリットを提示(例:「-5kg見え、魔法のワンピース」)
- 常識を覆す意外な事実を提示(例:「この料理、実は豆腐なんです」)
- 思わず目で追ってしまう美しい映像やインパクトのある効果音
- ターゲット層へ直接呼びかける(例:「北海道在住の30代女性へ」)
これらの仕掛けによって、ユーザーに「これは私のための動画だ」と認識させ、視聴を続ける動機付けを与えます。
ポイント2:音声なしでも伝わるテロップや視覚情報
多くのユーザーは、通勤中の電車内や職場の休憩中など、音を出せない環境でSNSを閲覧しています。
そのため、動画は「音声がオフの状態(サイレント再生)」でも内容が完全に伝わるように設計しなければなりません。
音声に頼らず情報を伝えるには、以下の視覚情報を活用します。
- 話している内容を補完する分かりやすいテロップ
- 感情が伝わる演者の豊かな表情や大きなジェスチャー
- 言葉だけでは分かりにくい情報を補うイラストや図解
- 商品の質感やサイズ感がリアルに伝わる接写映像
特にテロップは、単に音声を文字起こしするだけでなく、重要なキーワードの色を変えたりサイズを大きくしたりして、視覚的なアクセントを加えるのが効果的です。
テンポよく表示されるテロップは、動画にリズムを生み出し、視聴者を飽きさせない演出としても機能します。
ポイント3:【重要】各SNSに最適化された「動画サイズ・長さ」
各SNSプラットフォームには、それぞれ独自の文化と最適なフォーマットが存在します。
例えば、TikTokでYouTubeのような横長の長尺動画を投稿しても、ほとんど視聴されません。
成果を出すには、投稿するSNSに合わせた「動画サイズ(アスペクト比)」と「動画の長さ」の最適化が極めて重要です。
現在は、スマートフォンでの視聴が主流のため、画面いっぱいに表示される「9:16」の縦長動画が基本となります。
サイズが合っていない動画は没入感を損ない、ユーザーの離脱に繋がります。
主要SNSの推奨フォーマットと特徴は以下の通りです。
| SNS | 推奨サイズ (アスペクト比) | 推奨される長さ | 動画活用のポイント |
|---|---|---|---|
| Instagram (リール) | 9:16(縦長) | 15~60秒 | 美しい世界観とテンポの良い展開でファンを魅了 |
| TikTok | 9:16(縦長) | 15~60秒 | エンタメ性と冒頭のインパクトでトレンドを創出 |
| YouTubeショート | 9:16(縦長) | 15~60秒 | 「役立った」「面白い」と感じる学びや意外性を提供 |
| X (旧Twitter) | 16:9(横長) / 1:1(正方形) | 15~45秒 | リアルタイムな情報や話題性を即時に拡散 |
| 4:5 / 1:1 / 9:16 | 15秒~2分程度 | ターゲットに合わせた丁寧な情報提供で信頼を獲得 |
この表はあくまで一般的な目安であり、目的や内容に応じて最適な形式は変わります。
動画の長さについては、ユーザーの集中力が持続しやすい15秒~60秒程度の短尺が主流です。
しかし、商品の詳しい使い方を解説する場合など、情報量が多ければ2~3分程度の動画が有効な場合もあります。
伝えたいメッセージを整理し、最も効果的に伝わる長さを選択しましょう。
ポイント4:ユーザーに共感される「UGC風」の見せ方
UGCとは「User Generated Content」の略で、一般のユーザーが作成した口コミやレビューなどのコンテンツを指します。
企業が作る動画にも、この「UGC風」の要素を取り入れることで、広告特有の押し付けがましさをなくし、ユーザーからの共感と信頼を得やすくなります。
UGC風の動画を制作するには、以下のポイントを意識します。
- プロ用の機材ではなく、あえてスマートフォンで撮影したような自然な画質
- 完璧に整えられたスタジオではなく、生活感が感じられるリアルな背景
- プロのナレーターではなく、一般の人が話すような少し不器用だが正直な語り口
- 過度なエフェクトやテロップを避け、シンプルな編集
企業アカウントが「完璧な姿」を見せるだけでなく、少し隙のある「本音の姿」を見せることで、ユーザーは親近感を覚え、商品やサービスをより自分ごととして捉えてくれます。
ポイント5:視聴後の行動を促す「CTA(行動喚起)」の設計
動画で商品やサービスに興味を持ってもらっても、視聴後に何の行動も促さなければ、そこで関係は終わってしまいます。
そこで重要になるのが、CTA(Call To Action:行動喚起)の設計です。
動画の最後に、ユーザーに次にとってほしい具体的なアクションを明確に提示します。
CTAには、様々な種類があり、具体例は以下の通りです。
- 「詳細はプロフィールのリンクから」
- 「『気になる』とコメントで教えてね」
- 「参考になったら、いいねで応援お願いします」
- 「保存して後で見返してね」
- 「〇〇プレゼントキャンペーン実施中」
これらのCTAを動画の最後や概要欄に設置するだけで、Webサイトへのアクセス増加、エンゲージメント率の向上、そして最終的な売上向上へと繋がります。
動画の目的に合わせて、最も効果的なCTAを一つ、シンプルに設計しましょう。
SNS動画広告にかかる費用相場と料金体系
SNSで動画を活用する際の費用は、大きく「広告費(プラットフォームに支払う運用費)」と「動画の制作費」の2つに分かれます。
これらは全く別の費用であり、それぞれを正しく理解し、予算を配分する必要があります。
まずこのセクションでは、広告の成果に直結する「広告費」に焦点を当て、その仕組みや媒体ごとの費用相場、予算の考え方を詳しく見ていきましょう。
動画広告の費用を決める3つの課金方式
SNS動画広告の費用は、広告の目的や表示形式に応じて、主に3つの課金方式から選択されます。
課金形式の種類と概要、費用目安などは以下表の通りです。
| 課金方式 | 概要 | 費用相場の 目安 | メリット・目的 |
|---|---|---|---|
| CPM(インプレッション課金) | 広告が1,000回表示されるごとに費用が発生 | 500円~1,000円 / 1,000回 | 多くのユーザーに広告を見せたい認知拡大フェーズで有効 |
| CPC(クリック課金) | 広告が1回クリックされるごとに費用が発生 | 25円~100円 / 1クリック | Webサイトへの誘導や商品購入など、具体的な行動を促したい場合に有効 |
| CPV(視聴課金) | 動画が一定時間視聴されるごとに費用が発生 | 3円~20円 / 1再生 | 動画コンテンツそのものに興味があるユーザーに届けたい場合に有効 |
それぞれの特徴を理解し、広告の目的に合わせて最適なものを選ぶのが重要です。
どの課金方式が最適かは広告の目的によって異なり、媒体によっては複数の方式を組み合わせる場合もあります。
【媒体別】動画広告の費用相場一覧
各SNSプラットフォームは、それぞれ異なるユーザー層や文化を持つため、広告の費用相場も変動します。
主要なSNS広告の費用感と特徴は以下の表の通りです。
| SNS媒体 | 課金方式の主流 | 費用相場(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Instagram / Facebook | CPM, CPC | CPM: 500円~ / CPC: 50円~ | ・高精度なターゲティングが強み ・BtoCからBtoBまで幅広いビジネスで活用しやすい |
| TikTok | CPM, CPV | CPM: 100円~ / CPV: 5円~ | ・10代~20代の若年層へのリーチに強い ・拡散力が高く、認知拡大に向いている |
| X (旧Twitter) | CPM, CPC, CPV | CPM: 400円~ / CPC: 25円~ | ・リアルタイム性と高い拡散力が魅力 ・「いいね」やリポストによる二次拡散は課金対象外 |
| YouTube | CPV, CPC | CPV: 3円~ / CPC: 30円~ | ・幅広い年齢層にリーチ可能 ・一定時間視聴されないと課金されないフォーマットがある |
これらの相場は、広告を配信する業界の競争率や、ターゲット設定の絞り込み具合によって大きく変動します。
広告予算の決め方と費用対効果の考え方
広告予算に「これが正解」という金額はありませんが、一般的には以下の方法で予算を決定します。
- 目標から逆算して決める
(例:1件の顧客獲得に5,000円かけられる場合、目標10件なら予算5万円) - 少額でテスト配信し、成果を見ながら調整する
(例:まず月5万円で配信し、費用対効果の良い広告に予算を寄せる) - 売上に対する広告費の割合を決めておく
(例:売上の10%を広告費に充てる)
特に初めてSNS広告を出す場合は、まず月5万~10万円程度の少額予算でテストマーケティングから始めるのがおすすめです。
そして重要なのが、費用対効果の考え方です。ROAS(広告費用対効果)やCPA(顧客獲得単価)といった指標を常に確認しましょう。
「どの動画が」「どのターゲットに」「いくらで」成果を出しているのかを分析し、継続的に改善していく姿勢が求められます。
SNS動画制作|内製(自社)と外注(制作会社)の徹底比較
SNS動画のクオリティは、広告効果やブランドイメージを大きく左右する重要な要素です。
動画制作には「自社で作る(内製)」と「プロに頼む(外注)」の2つの選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
自社の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
自社で制作(内製)するメリット・デメリット
内製は、コストを抑えつつスピーディーに動画を量産したい場合に有効な選択肢です。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| コスト | ・外注費を大幅に削減できる ・低予算で多くの動画を制作可能 | ・撮影機材や編集ソフトへの初期投資が必要 ・担当者の人件費が発生 |
| スピード | ・修正や変更に迅速に対応可能 ・トレンドに合わせた動画を即時に作れる | ・担当者のスキルに品質が大きく依存 ・担当者の異動や退職でノウハウが失われるリスク |
| 内容理解 | ・自社の商品やサービスへの理解が深い ・企業の熱量や想いを直接反映できる | ・客観的な視点が欠け、独りよがりな内容になりがち |
特に、スピード感が重視されるTikTokやInstagramリールの投稿には、内製が向いています。
プロの制作会社に依頼(外注)するメリット・デメリット
外注は、高品質な動画で確実に成果を出したい場合や、社内にリソースがない場合に適しています。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 品質 | ・高品質で訴求力の高い動画が期待できる ・専門的な撮影や最新の編集技術を活用できる | ・制作会社によってスキルや得意分野に差がある ・イメージの共有が不十分だと期待通りにならない |
| リソース | ・自社のリソース(人・時間)を消費しない ・担当者は本来のコア業務に集中できる | ・制作費用が高額になりやすい ・制作進行におけるコミュニケーションコストが発生 |
| 戦略性 | ・第三者の客観的な視点で自社の魅力を引き出せる ・マーケティング戦略に基づいた動画制作を提案してくれる | ・修正に時間や追加費用がかかる場合がある |
ブランドイメージを左右する広告動画や、企業の顔となる紹介動画などは、プロに依頼するのが安心です。
失敗しない制作会社の選び方と費用相場
外注で成果を出すには、信頼できるパートナー(制作会社)選びが最も重要です。
以下のポイントを確認し、慎重に選定しましょう。
- 作りたい動画のテイストと制作会社の実績ポートフォリオが合っているか
- SNS動画マーケティングに関する知見や成功実績は豊富か
- コミュニケーションは円滑で、担当者の対応は誠実か
- 見積もりの内訳は明確で、料金体系は分かりやすいか
必ず複数の会社から相見積もりを取り、提案内容や担当者の対応を比較検討しましょう。
制作費用は、動画の内容によって大きく変動します。
- 簡易な動画(撮影なし・編集のみ):5万円~20万円
- 簡単な撮影あり(インタビューなど):20万円~50万円
- 企画・構成から含む本格的な動画:50万円~
費用は、企画内容、撮影日数、演者の有無、CGの使用などで変わります。
まずは自社の予算感と、どこまでの作業を依頼したいかを明確にして相談してみましょう。
よくある質問
最後は、SNSの動画広告に関してのよくある質問を紹介します。
SNS広告の基本的な質問を押さえているので、しっかり確認していきましょう。
SNS動画に最適な長さ(時間)は結局何秒ですか?
結論から言うと「目的とSNSによる」が答えですが、一般的には15秒〜60秒が主流です。
特にTikTokやInstagramリールでは、ユーザーが次々とスワイプするため、短くテンポの良い動画が好まれます。
最も重要なのは冒頭の1〜3秒で興味を引くことです。
この「つかみ」さえ成功すれば、有益な情報や面白いストーリーであれば1分を超える動画でも視聴されます。
まずは15秒前後を目安に、伝えたい情報量に合わせて調整し、視聴維持率などのデータを見ながら最適解を探していくのが良いでしょう。
動画の推奨サイズはどのくらい?
現在のSNS動画は、スマートフォンでの視聴がほとんどのため、画面いっぱいに表示される「9:16」の縦長サイズが推奨されます。
具体的には1080×1920ピクセルが一般的です。
このサイズはInstagramリールやTikTok、YouTubeショートの標準であり、ユーザーの没入感を最大限に高めます。
サイズが合っていないと上下に黒帯が表示され、視聴者の離脱に繋がる可能性があるので注意しましょう。
ただし、X(旧Twitter)やFacebookのフィードでは1:1の正方形サイズも依然として有効です。
まずは基本の9:16で作成しましょう。
動画を活用しても効果が出ない原因は何ですか?
効果が出ない最大の原因は「ユーザー目線の欠如」です。
企業が伝えたいことだけを話す動画は敬遠されます。
具体的には、以下の点が考えられます。
- 冒頭の1〜3秒で興味を引けていない
- ターゲットが曖昧で誰にも響かない
- SNSの文化に合わない(例: TikTokで宣伝色が強い)
- 音声オフで意味が伝わらない
- 視聴後の行動を促していない
動画は「ユーザーの時間をいただく」という意識が重要です。
面白い、役に立つといった価値を提供できているか、客観的に見直しましょう。
まとめ
本記事では、SNS動画の作り方や、インスタなどをはじめとしたSNS動画の最適な長さや、SNS広告への出稿費用を解説しました。
まとめると以下の4点になります。
- SNSの動画制作は最初の1~3秒で心を掴む「冒頭の仕掛け」が特に重要
- SNS動画の特徴や課金方式はそれぞれのSNSによって異なる
- SNS広告費用は自由に決められるが、月5万~10万円程度の少額予算からはじめるのがおすすめ
- 自社にノウハウがない場合は他社にSNS動画制作を依頼するのも選択肢
SNSの動画広告は、動画制作も含めて一定の費用がかかります。
それだけに慎重に検討を進めるようにしてください。
SNSの動画広告出稿に興味が出たら、どのSNSでどのくらいの広告費用がかかるか各SNSのヘルプページなどを確認してみてはいかがでしょうか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品や自社サービスをさらに販売できる!/