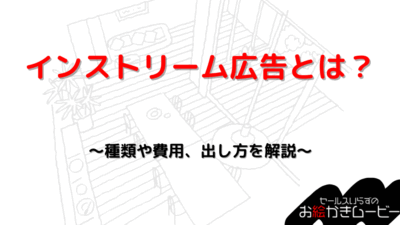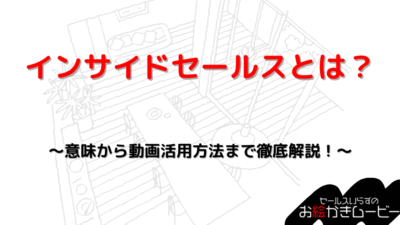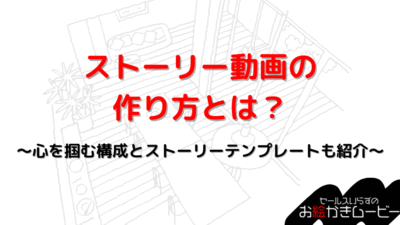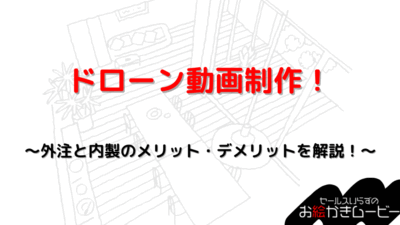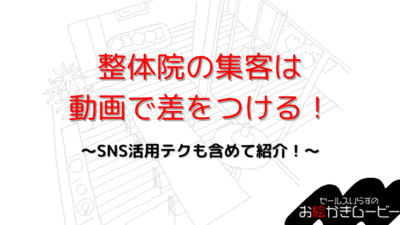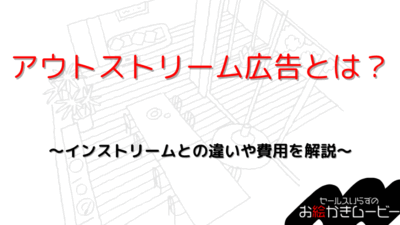購買意欲を掻き立てる動画制作とは?心を動かす言葉と色の使い方も解説!
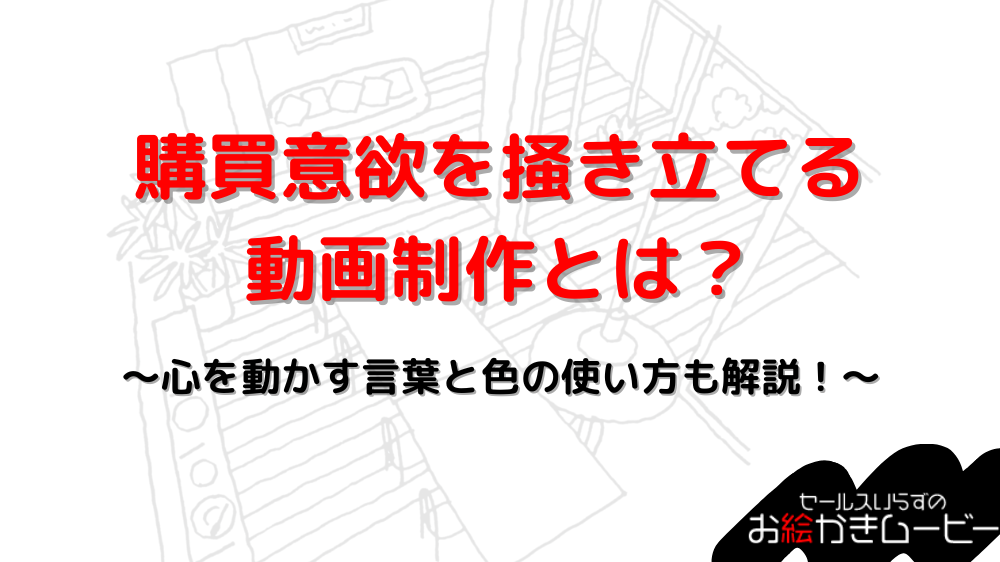
見ているうちに、つい「コレ欲しい!」と思ってしまう動画を、一度は見たことがあるのではないでしょうか。
短い時間で心を動かし、購買意欲を高める動画には、じつは巧みに計算された演出が施されています。
本記事では、思わず商品が欲しくなる「購買意欲を掻き立てる動画」の作り方をご紹介します。
あわせて、以下の視聴者の心を動かすための重要なポイントについても解説します。
- 心をつかむ言葉選び
- 色使いのコツ
- 消費者心理学
- 買いたくなるキャッチコピー
動画で商品やサービスの売上アップを目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/
購買意欲を掻き立てる動画とは?その重要性
現代において、動画は日常生活とビジネス面で欠かせないツールとなりました。
なかでも、見る人の購買意欲を掻き立てる動画は、企業にとって売上アップの大きな鍵を握っています。
そこで本記事では、購買意欲を掻き立てる動画の重要性について、以下の3つに分けて解説していきます。
- なぜ今、動画コンテンツが重要視されるのか
- 購買意欲を掻き立てるの意味と心理的背景
- 動画がもたらす具体的なビジネス効果とは
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
なぜ今、動画コンテンツが重要視されるのか
動画コンテンツが重要視される理由として、主に以下の3つが挙げられます。
- 圧倒的な情報伝達能力
- 検索エンジンの優遇
- 5Gの普及による視聴環境の改善
まず、動画は静止画や文章に比べて、約5000倍もの情報を伝えられると言われています。
短時間で多くの情報を届けられるため、視聴者に強い印象を与えることが可能です。
さらに、検索エンジンのアルゴリズム変更により、動画を含むコンテンツは検索結果で上位に表示されやすくなっています。
そして5Gの普及により、通信速度が格段に向上しています。
場所を選ばず、より快適に動画を視聴できるようになったことも、動画の活用が進んでいる大きな要因です。
購買意欲を掻き立てる意味と心理的背景
購買意欲とは、商品やサービスを買いたいという消費者の欲求を指します。
この欲求は、心理状態や季節、イベントなどの外部の影響によって変化するのが特徴です。
例えば、季節の変わり目に服が欲しくなったり、クリスマス前にプレゼントが買いたくなったりする現象です。
このように、購買欲求は心理的背景によって常に変動しているため、購買意欲を引き出す工夫を動画や広告に取り入れることが大切になってきます。
動画がもたらす具体的なビジネス効果とは
本記事では動画がもたらす具体的なビジネス効果について、以下の3つをご紹介します。
- ブランド認知の拡大
- 購買率・成約率の向上
- 業務効率化とコスト削減
動画だと商品・サービスへの理解が深まり、購買につながりやすくなります。
購入意欲と購買意欲の違いを理解しよう
「購入意欲」と「購買意欲」はよく似た言葉ですが、実は意味に違いがあります。
どちらも商品やサービスに対する興味を表しています。
ですが、心理的な温度感や実際の行動に移すまでの距離に差があるのが特徴です。
本記事ではこの2つの違いについて、以下の3つの視点から分かりやすく解説します。
- 「購入意欲」が示す顧客の心理状態
- 「購買意欲」を正しく理解し使い分ける
- ビジネスシーンでの適切な使い方と例文
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
「購入意欲」が示す顧客の心理状態
「購入意欲」とは、商品やサービスに対して「欲しい」「気になる」と感じている段階の心理状態を指します。
まだ明確な購入の意思や行動には至っていないものの、興味や関心が芽生えている状態です。
たとえば、新商品の広告を見て「いいかも」と感じる、SNSで話題の商品に興味を持つといったケースが該当します。
この段階では、情報収集や比較検討を行う人が多く、適切なアプローチによって購買意欲へとつなげることが可能です。
「購買意欲」を正しく理解し使い分ける
「購買意欲」とは、実際に商品やサービスを「買おう」とする具体的な意思を持った状態を指します。
すでに比較や検討を終えており、あとは購入のタイミングや条件が整えばすぐに行動に移す段階です。
一方で「購入意欲」はまだ関心レベルにとどまる場合が多く、両者は行動への距離に違いがあります。
この違いを理解し、見込み顧客の心理状態に応じて使い分けることで、より効果的なマーケティング施策が可能になります。
ビジネスシーンでの適切な使い方と例文
「購入意欲」と「購買意欲」は、顧客の行動段階に応じて使い分けることが重要です。
たとえば、広告やSNSで反応があった段階では「購入意欲が高まっている」と表現します。
一方で、すでに商品ページを閲覧したり、カートに入れているような行動には「購買意欲が高い」といった言い回しが適しています。
【例文】
・このキャンペーンで購入意欲を喚起しましょう。
・サイト訪問者の購買意欲を分析し、コンバージョン率の改善を図る。
状況に応じた言葉の使い分けが、的確なマーケティング戦略につながります。
動画で活用できる!買いたくなる消費者心理学
感情や行動に影響を与える心理法則を理解し、動画に取り入れることで、購買意欲を自然と高めることが可能になります。
本記事では、動画で活用できる「買いたくなる消費者心理学」を以下の5つ紹介します。
- 損失を回避したい「プロスペクト理論」
- 多くの人が選ぶものを選ぶ「バンドワゴン効果」
- お返しをしたくなる「返報性の原理」
- 専門家や権威を信じる「権威への服従原理」
- 限定品に惹かれる「希少性の法則」
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
損失を回避したい「プロスペクト理論」
人は「得をする」より「損をしない」ことに強く反応する傾向があります。
これがプロスペクト理論であり、マーケティングにおいて非常に効果的な心理です。
たとえば「今買わないと損をする」「セールは本日限り」といった訴求は、この心理に基づいたものです。
単にお得さを伝えるだけでなく、今行動しなければ損をするという感情を刺激することで、購買を後押しできます。
希少性や緊急性を強調する表現を組み合わせることで、さらに強い効果が期待できます。
多くの人が選ぶものを選ぶ「バンドワゴン効果」
バンドワゴン効果とは、人が多くの人に支持されているものを自然と選びたくなる心理現象です。
これは「みんながやっているから自分も」という集団への帰属意識から生まれます。
マーケティングでは、「多数の顧客が支持」「SNSで話題」などの表現を使い、商品の信頼性や魅力を高めるのに活用されます。
口コミやレビューと組み合わせることで、さらに説得力が増し、購買意欲を効果的に刺激できます。
お返しをしたくなる「返報性の原理」
返報性の原理とは、人が誰かから好意や恩恵を受けると、自然とお返しをしたくなる心理のことです。
この仕組みをマーケティングに活かすことで、顧客との良好な関係を築きやすくなります。
例えば、無料サービスやプレゼントを提供することで、顧客は感謝の気持ちからリピートや購入につながりやすくなります。
また、クーポンの配布なども返報性を促す効果的な手法です。
この原理を上手に使うことで、企業と顧客双方にとって満足度の高い関係が生まれます。
専門家や権威を信じる「権威への服従原理」
権威への服従原理とは、人が専門家や公的機関など権威ある存在の意見や推奨を信頼し、購買行動に影響を受ける心理です。
この心理を利用することで、商品の信頼性や説得力を高めることができます。
具体的には、専門家の推薦コメントを掲載したり、有名人を広告に起用したり、公的な認証をアピールする方法があります。
特に新技術や専門的な商品では、権威の証明が購入の後押しとなるため効果的です。
限定品に惹かれる「希少性の法則」
希少性の法則は、人が手に入りにくいものに価値を感じ、強く惹かれる心理を指します。
数量限定や期間限定の商品、会員限定の特典などがこの効果を利用した代表例です。
「今だけ」「限定販売」といった表現は、購入の機会を逃すことへの焦りを生み、購買意欲を高めます。
この法則を上手に活用することで、商品やサービスの魅力を一層引き出し、売上アップにつなげることが可能です。
思わず買いたくなる言葉とキャッチコピーの作り方
魅力的な言葉やキャッチコピーは、商品の魅力を一瞬で伝え、消費者の心をつかむ大切な要素です。
しかし、効果的なコピー作りは簡単ではありません。
言葉の選び方や表現の工夫、ターゲットの心理を理解することが成功の鍵となります。
そこで本記事では、思わず買いたくなる言葉とキャッチコピーの作り方について、以下の5つのポイントについて解説します。
- 視聴者の感情に響く言葉選びのテクニック
- 動画で使える買いたくなるキャッチコピー例
- ベネフィットを伝えるストーリーテリング
- 行動を促す効果的な言葉の言い換え表現
- 動画のナレーションやテロップに活かす例文
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
視聴者の感情に響く言葉選びのテクニック
視聴者の心を動かす言葉にはいくつかのポイントがあります。
本記事では、以下の3つを紹介します。
- 手に入れた後の具体的なメリットを示す
- 希少性や特別感を強調する
- 信頼を築くための裏付けを提示する
購入後に得られる効果や理想の姿を具体的に伝えることで、視聴者の興味を引きましょう。
また、限定的な要素を強調して「今すぐ手に入れたい」と感じさせる心理を刺激します。
さらに、専門家や有名人の推薦を活用することで、商品の信頼性と安心感を高めることが可能です。
これらを上手く活用することで、視聴者の心に響き、購買意欲を大きく引き出す言葉選びが実現できます。
動画で使える買いたくなるキャッチコピー例
購買意欲を高めるキャッチコピーには、以下のような表現があります。
- 売上No.1
- 先着100名限定
- 今から○○分限定のお値段
- あの○○が認めた一品
- 今だけ!1つ買うと1つ無料
- 本日のみ~
ターゲットのニーズに合わせて言葉を選びましょう。
単独ではなく、組み合わせて使うのもおすすめです。
ベネフィットを伝えるストーリーテリング
ベネフィットとは、商品やサービスを利用することで得られる「価値ある未来」や「嬉しい変化」のことです。
それを伝えるにはただ機能を並べるだけで、有効なのがストーリーテリングです。
実際の体験や変化を物語として描くことで、視聴者は自分の生活に置き換えて想像しやすくなります。
共感と感情が動くことで、ベネフィットの魅力がよりリアルに伝わり、購買意欲を高める力になります。
行動を促す効果的な言葉の表現
行動を促すには、「今すぐやりたい」「やってみよう」と思わせる具体的な言葉選びがカギになります。
以下に、実際によく使われる表現をご紹介します。
- 今すぐ無料で試す
- 簡単3ステップで完了
- あなたも〇〇できます
- 〇〇するだけでOK!
- 残りわずか!お急ぎください
これらの言葉をうまく組み合わせることで、自然な形で顧客の行動を後押しが可能です。
動画のナレーションやテロップに活かす例文
動画のナレーションやテロップは、視聴者の心に響くメッセージを届けるための大切なポイントです。
短くわかりやすい言葉や、メリットを具体的に示す表現を用いましょう。
以下が動画のナレーションやテロップに活用できる、例文です。
- 「今だけ限定!お見逃しなく」
- 「初回購入特典付き」
- 「送料無料キャンペーン実施中」
- 「たった○分で効果を実感」
- 「お客様満足度○○%」
- 「専門家も推薦」
これらのフレーズをナレーションやテロップに取り入れることで、視聴者の興味を引きつけることができます。
購買意欲を高めやすくなるので、ぜひ活用してください。
購買意欲を高める色とデザインの戦略
私たちは、無意識のうちに色やデザインから強い影響を受けています。
実際、色彩やレイアウトの選び方ひとつで、顧客の印象や購買意欲は大きく左右されるのです。
本記事では、購買意欲を高めるための色とデザインの戦略について、以下の5つの視点から解説していきます。
- 色が人の心理や行動に与える影響とは
- 動画で実践できるカラーマーケティングの効果
- 女性の購買意欲を刺激する配色とは
- 男性の購買意欲に響く色の使い方
- 視線を惹きつける魅力的なデザインのコツ
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
色が人の心理や行動に与える影響とは
色は視覚的な印象だけでなく、感情や行動にも大きな影響を与える力があります。
主な色の効果は、以下のとおりです。
| 色 | 効果・特徴 |
|---|---|
| 赤 | 交感神経を刺激体温・脈拍の上昇など |
| 青 | 神経を落ち着かせる体温の低下など |
| 緑 | リラックス効果安心感が増える |
| 黄色 | 集中力のアップ明るい気分になる |
| 紫 | 優雅さを与える高貴な印象 |
色の特徴を理解し活用することで、購買意欲や行動を効果的に促せます。
動画で実践できるカラーマーケティングの効果
動画でのカラーマーケティングには、視覚的な訴求力を活かし、視聴者の感情や行動に直接働きかける効果があります。
色彩の使い分けによって、ブランドイメージの強化や商品の魅力アップが可能です。
例えば、暖色系は興奮や購買意欲を高め、寒色系は安心や信頼を与えます。
動画の中で効果的に色を配置することで、メッセージが視覚的に伝わりやすくなる効果があります。
これにより、商品の認知度向上や購買行動の促進につながるのです。
女性の購買意欲を刺激する配色とは
女性の購買意欲を刺激する配色には、落ち着いた「くすみ色」と明るく親しみやすい「ピンク」が効果的です。
くすみ色は上品で洗練された印象を与えます。
一方、ピンクは「かわいい」という感情を呼び起こし、ターゲット層の購買意欲を自然に促すことが可能です。
目的に合わせてこれらの色を使い分けたり、組み合わせたりしてみてください。
男性の購買意欲に響く色の使い方
男性の購買意欲を刺激する配色には、黒を基調としたダークトーンや寒色系、金属的なカラーが効果的です。
男性は明るく柔らかな色よりも、落ち着いたグレイッシュトーンや深みのある色合いを好む傾向があります。
ダークな背景にアクセントとなるポイントカラーを組み合わせることで、メリハリが生まれ、商品の魅力を強調しやすくなります。
こうした配色は、男性向けの広告やサイトで特に購買意欲を高める役割を果たすでしょう。
視線を惹きつける魅力的なデザインのコツ
視線を効果的に誘導するデザインは、情報をスムーズに伝えるうえで重要です。
視線を惹きつけるデザインのコツを、以下にまとめました。
| コツ | 説明 |
|---|---|
| 視線パターンを活用する | ・Zの法則(横書きレイアウトで左上から右下へ視線を誘導) ・Fの法則(Webサイトなどで必要情報を効率的に見せる) ・Nの法則(縦書きレイアウトに適した視線誘導) |
| トンネル効果 | ・中央を明るくして周囲を暗く ・目立たせたい部分を際立たせる |
| 人物・矢印の視線利用 | ・矢印の方向や人物の視線を強調したい部分に向ける ・視線を誘導 |
これらのテクニックを活用して魅力的なデザインを作りましょう。
動画の印象を決定づける音楽・BGMの力
動画制作において、音楽やBGMは視聴者の印象を大きく左右する重要な要素です。
動画の効果を高めるためには音楽選びが欠かせません。
本記事では、動画の印象を決定づける音楽・BGMについて、以下の3つに分けて解説していきます。
- 音楽やBGMが購買行動に与える心理的効果
- 購買意欲を掻き立てる曲の選び方と具体例
- アップテンポな曲とスローな曲の使い分け
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
音楽やBGMが購買行動に与える心理的効果
音楽やBGMは視聴者の感情に直接働きかけ、購買行動に影響を与える力を持っています。
心地よいメロディはリラックス感や安心感を生み、購買への心理的ハードルを下げます。
また、テンポによって時間の感じ方も変わり、滞在時間や視聴時間を自然に延ばすことが可能です。
さらに、印象的な音楽はブランド体験と結びつきやすく、記憶に残るきっかけになります。
適切な音選びが、購買意欲の向上に直結するのです。
購買意欲を掻き立てる曲の選び方と具体例
商品のイメージに合ったBGMを選ぶことで、購買行動に大きな影響を与えることができます。
たとえば、クラシック音楽は「高級感」や「洗練された印象」を与え、高価格帯の商品を選ばせやすくします。
ある実験では、ワインショップでフランス音楽を流すとフランスワインの売上が、ドイツ音楽を流すとドイツワインの売上が増加しました。
これは、音楽が無意識に商品イメージと結びつき、選択に影響するためです。
音楽は感情を動かし、商品の魅力を無意識に引き立てる強力な仕掛けの一つといえます。
アップテンポな曲とスローな曲の使い分け
BGMのテンポは、来店者の行動や滞在時間に大きな影響を与えます。
| テンポの種類 | 主な効果 | 適したシーンの例 |
|---|---|---|
| アップテンポな音楽 | ・活発な印象を与える ・購買ペースを促進 | ・混雑時の店舗 ・短時間で回転したい売場 |
| スローテンポな音楽 | リラックス効果滞在時間の延長 | ・高価格帯商品の売場 ・滞在促進を狙う空間 |
目的に応じてテンポを使い分けると、購買体験をコントロールが可能です。
最終的に、売上アップにつなげることができるでしょう。
購買意欲を掻き立てる動画制作の実践ステップ
では購買意欲を掻き立てる動画を制作するに、どのようなステップで制作していけばいいでしょうか。
本記事では、動画制作の実践ステップとして以下の4つに分けて解説していきます。
- 動画制作は内製?外注?メリット・デメリット
- 動画制作会社を選ぶ際の重要なポイント
- ターゲットに合わせた動画の最適な長さ
- 公開後の効果測定と改善を繰り返す重要性
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
動画制作は内製?外注?メリット・デメリット
動画制作には「内製」と「外注」という2つの選択肢があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、詳細を以下にまとめました。
| 項目 | 内製 | 外注 |
|---|---|---|
| メリット | ・社内で柔軟に修正・対応できる ・ノウハウが蓄積できる | ・プロ品質で仕上がる ・専門機材や人材を活用できる |
| デメリット | ・時間と手間がかかる ・スキルが不足すると品質が落ちる | ・コストが高い傾向 ・担当者とコミュニケーションが取れない |
目的や予算、社内のリソースを踏まえ、自社にあった動画制作方法を選びましょう。
動画制作会社を選ぶ際の重要なポイント
動画制作会社を選ぶ際は、以下のポイントを押さえてください。
- 提案力があるかどうか
- 過去の制作実績が自社のイメージに合っているか
- 得意な業種・ジャンルの傾向を把握
- 対応力と柔軟性があるか
- コミュニケーションが円滑に取れるか
- 納期や費用の明確さ
動画制作会社を選ぶ際は、こちらの目的や課題に対して的確な提案ができるかを確認しましょう。
ポートフォリオを通じて、トーンやクオリティの相性も見極めることが大切です。
自社の業界に理解がある会社なら、進行もスムーズです。
また、スケジュール調整や修正対応の柔軟性、担当者とのやり取りの円滑さも完成度に大きく影響します。
追加費用や納期についても事前に確認しておくと安心です。
ターゲットに合わせた動画の最適な長さ
プラットフォームごとに視聴者の特性が異なるため、動画の長さや構成も最適化が必要です。
以下はプラットフォームごとの、ターゲットに合わせた最適な動画の長さです。
| プラットフォーム | 利用ユーザーの年代 | 最適な長さ |
|---|---|---|
| YouTube | 幅広い世代が利用 | 5~20分ほど(動画のテーマによる) |
| 10代〜30代 | 15~30秒ほど | |
| TikTok | 10代〜20代 | 15~60秒ほど |
| X | 10代〜30代 | 15~45秒ほど |
プラットフォームごとの特性を活かし、目的と視聴者に合った尺を意識しましょう。
公開後の効果測定と改善を繰り返す重要性
動画公開後の効果測定と改善は、成果を最大化するうえで欠かせません。
再生回数や視聴維持率、クリック率などの指標を分析することで、視聴者の反応や離脱ポイントが可視化されます。
データをもとにタイトルやサムネイル、構成を見直しましょう。
次回以降のパフォーマンス向上につながります。
動画を公開して終わりではなく、検証と改善を繰り返してください。
そうすることで、動画施策はより強固なものになるのです。
よくある質問
本記事では購買意欲を掻き立てる動画制作について、よくある質問(以下の5つ)に回答していきます。
- 動画制作にかかる費用の相場はどれくらいですか?
- 「購買意欲を煽る」表現は避けるべきですか?
- 著作権フリーで使える音楽や素材はありますか?
- 動画の効果測定はどのような指標を見ればいいですか?
- 制作した動画はどのプラットフォームで公開すべきですか?
それぞれ、1つずつ回答していきます。
ぜひ参考にしてください。
動画制作にかかる費用の相場はどれくらいですか?
動画制作にかかる費用の相場は、動画のジャンルによって大きく変わります。
以下の表は、ジャンル別の動画制作費用の相場です。
| 動画の目的 | 費用の目安(動画1本の制作費用) |
|---|---|
| YouTube(編集のみ) | 5,000〜50万円 |
| 商品・サービス紹介 | 10〜200万円以上 |
| 会社・店舗・学校紹介 | 10〜200万円以上 |
| 採用 | 10〜200万円以上 |
| セミナー・イベント | 5〜50万円以上 |
| アニメーション | 10〜300万円以上 |
| テレビCM | 100〜500万円以上 |
| 研修動画 | 5〜200万円 |
| VR動画 | 20〜550万円 |
引用:動画幹事
実際は動画制作会社を利用するか、フリーランスに制作を依頼するかによっても、費用は変わってきます。
動画制作を依頼する際は、しっかりと見積もりをとって確認しましょう。
「購買意欲を煽る」表現は避けるべきですか?
「購買意欲を煽る」表現は、使い方に注意が必要です。
過度な表現や誇張は、消費者に不信感を与える可能性があります。
特に根拠のない煽りや不安をあおるような表現は避けましょう。
消費者目線を大切にし、誠実で納得感のある表現を心がけましょう。
著作権フリーで使える音楽や素材はありますか?
はい、著作権フリーで使える音楽や素材は多数存在します。
以下に、おすすめの素材サイトと音楽サイトをまとめました。
【素材サイト】
【音楽サイト】
利用条件などはサイトによって異なるため、使用する際は必ず利用規約を確認しましょう。
動画の効果測定はどのような指標を見ればいいですか?
動画の効果測定には、様々な指標があります。
本記事では、動画分析で特に押さえておきたい主な指標項目を以下にまとめました。
| 指標名 | 内容 |
|---|---|
| 視聴回数 | ・動画が何回再生されたかを示す |
| 完全視聴率 | ・最後まで視聴された割合 |
| クリック数 | ・動画内の広告が何回クリックされたか |
| コンバージョン数 | ・資料請求や購入など ・視聴者が最終的に取った成果につながる行動の回数 |
| 表示回数 | ・サムネイルが表示された回数 |
これらの指標を組み合わせて分析することで、動画のどこが効果的だったか、どこを改善すべきかを明確にすることができます。
動画を一度出して終わりにするのではなく、必ず効果測定をして次に活かすようにしてください。
制作した動画はどのプラットフォームで公開すべきですか?
動画を公開する場所は、狙いたい視聴者や目的に合わせて選ぶことが重要です。
若い世代にはYouTubeやInstagramリール、X(旧Twitter)が効果的です。
一方、ビジネス向けならFacebookが適しています。
短い動画ならYouTubeショートやTikTokも有効です。
さらに、自社サイトやランディングページに動画を設置すると、商品の理解促進や購買につながりやすくなります。
ターゲットと目的を明確にし、最適なプラットフォームを選びましょう。
まとめ
本記事では、購買意欲を掻き立てる動画制作について解説してきました。
本記事をまとめると、以下の3点です。
- 動画は視覚・聴覚を同時に刺激し、圧倒的な情報伝達力を持つ
- 購買行動に影響する心理学(希少性、返報性、権威など)を戦略的に活用する。
- 色彩・デザイン・音楽といった演出要素が、感情や印象を左右する
視聴者の購買意欲を掻き立てることができれば、売上アップが見込めます。
そのためには、戦略的な構成と心理に響く演出を意識することが重要です。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/