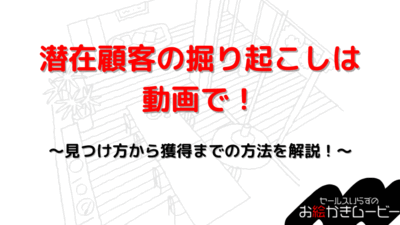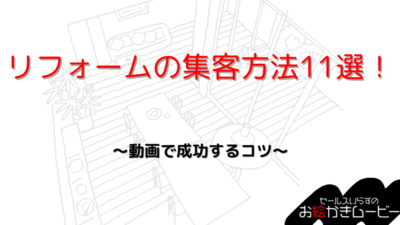動画コンテンツとは?作り方から活用法・配信先まで解説!
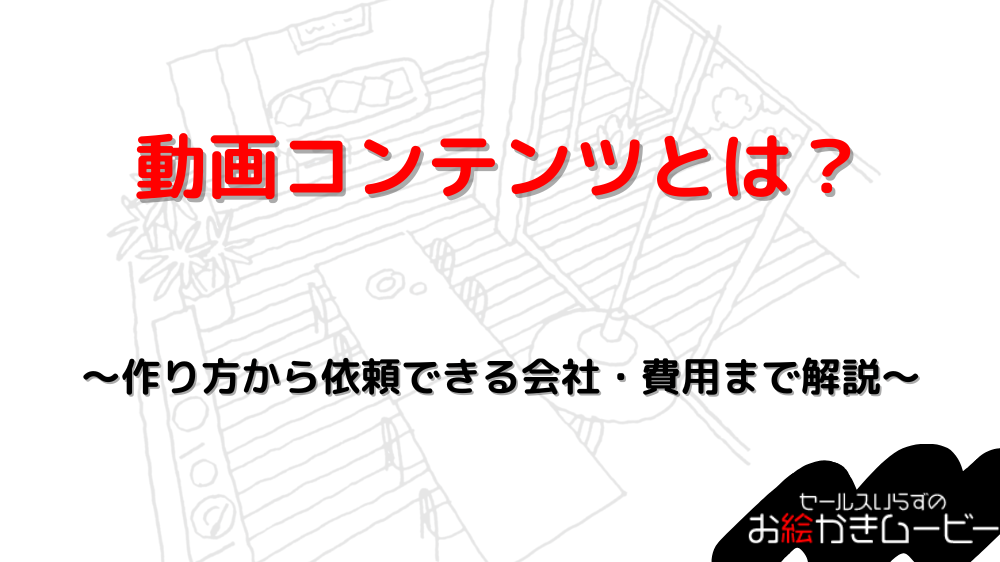
動画コンテンツとは、映像と音声で構成されたデジタルコンテンツです。
NetflixやYouTube、TikTokなどで見かけるように、企業から個人まで幅広く制作されています。
また、動画は視覚と聴覚に訴えるため、ブランディングや商品の魅力発信としても効果的です。
本記事では、動画コンテンツの基本から、作り方・活用法・配信先までをわかりやすく解説します。
「自分でも制作してみたい」「動画コンテンツ作りに興味がある」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/
動画コンテンツとは?
先ほども述べた通り、動画コンテンツとは、映像と音声で構成されたデジタルコンテンツです。
映画やテレビ番組、アニメ、ミュージックビデオ、オンライン講座、YouTube動画など、様々な形式が存在しています。
動画コンテンツの強みともいえる特徴は以下の3点です。
- 視覚と聴覚に訴える情報伝達手段
- 多様なジャンルとプラットフォーム
- 視聴者エンゲージメントを高める効果
上記の特徴が具体的にどのようなことなのか、次から詳しく解説していきます。
視覚と聴覚に訴える情報伝達手段
動画コンテンツは、視覚と聴覚の両方に訴えかけることで、他の情報伝達手段よりも豊かな情報を効果的に伝えることができます。
特に視覚に関して説明すると、動きや色彩や構図という観点から以下の表の特徴が見られます。
| 動き | ・映像は静止画とは異なり、動きで表現可能 ・物事の変化や過程を直感的に理解させられる |
| 色彩 | ・感情や雰囲気を表現できる ・視聴者の印象に強く残る ・例として鮮やかな色彩は楽しさや興奮を、落ち着いた色彩は安心感や信頼感を演出する |
| 構図 | ・視線の誘導や情報の整理に役立つ ・適切な構図は、視聴者の注意を引きつけられる ・構図が良いと、情報を分かりやすく伝えられる |
聴覚に関しての特徴やその詳細は以下の表の通りです。
| 音声 | ・ナレーションやセリフにより情報を直接的に伝えられ、視聴者の理解が深まる ・話者の声質や話し方は感情や信頼感を視聴者に与える効果がある |
| 音楽 | ・映像の雰囲気を盛り上げ、感情を喚起する ・適切な選曲は、映像の内容を補完し、視聴者の没入感を高める |
| 効果音 | ・映像に臨場感を与え、現実感を高める ・ドアの開閉音や足音など、細かな音も視聴者の体験を豊かにする |
視覚と聴覚の要素が組み合わさると、動画コンテンツは、情報を多角的に伝え、視聴者の感情に訴えかける強力な情報伝達手段になります。
テキストの5000倍ともいわれる情報量
動画コンテンツは、テキストの約5000倍もの情報を伝えられると言われるほど、情報伝達力に優れています。
映像・音・文字を組み合わせることで、視覚と聴覚の両方に働きかけることができます。
そのため、短時間でも印象に残りやすく、視聴者に深い理解を与えて感情にも訴えることが可能です。
視聴者エンゲージメントを高める効果
動画コンテンツは、視聴者のエンゲージメント(積極的な関与)を高める効果があります。
具体的には、期待できる効果は以下の通りです。
- 記憶への定着:文字情報よりも記憶に残りやすい傾向がある
- 感情の喚起:視聴者の感情を揺さぶり、共感を生み出せる
- 行動促進:視聴者に直接的な行動を促す効果がある
- 共有・拡散:視聴者の関心を惹けた動画コンテンツは、SNSなどで共有・拡散されやすい
上記の効果は、企業などにおいて、マーケティングやブランディング、教育など、様々な分野で活用されています。
動画コンテンツは、視聴者とのエンゲージメントを高め、より深い関係を築くための強力なツールと言えるでしょう。
企業が動画コンテンツを活用する5つのメリット
企業が動画コンテンツを活用することで、様々なメリットがあります。
本記事では、以下の5つのメリットについて解説していきます。
- 売上・コンバージョンの向上
- ブランディング・認知度向上
- 採用活動の効率化
- 教育・研修コストの削減
- SNSでの情報拡散(バイラル効果)
それぞれ、1つずつ確認していきましょう。
①売上・コンバージョンの向上
企業が動画コンテンツを活用すると、売上やコンバージョンの向上が期待できます。
ここでいうコンバージョンとは、「会員登録」や「問い合わせ」など、企業が望むお客様の具体的な行動のことです。
動画は商品やサービスの魅力をわかりやすく伝え、視聴者の購買意欲を高めます。
さらに、実際の使い方や口コミを見せることで信頼感が増し、購入や問い合わせの増加につながる効果的な手段です。
②ブランディング・認知度向上
動画コンテンツは、企業のブランディングや認知度向上に効果的な手段です。
映像を通じて、企業の世界観や大切にしている想いを直感的に伝えることができ、視聴者に強く印象づけることが可能です。
また、テキストや画像では伝わりにくいニュアンスや雰囲気も映像なら表現できるため、ブランドイメージの統一や魅力づけにも大きく貢献します。
③採用活動の効率化
動画コンテンツは、企業の採用活動においても大きな効果を発揮します。
職場の雰囲気や社員の声、働く様子をリアルに伝えることで、求職者とのミスマッチを防ぎ、応募の質を高めることが可能です。
また、説明会や面接で繰り返し伝える内容を動画で共有することで、採用担当者の業務負担を軽減し、効率的な採用活動が可能になります。
④教育・研修コストの削減
動画コンテンツを活用することで、社員教育や研修のコスト削減が可能です。
研修内容を動画化すれば、いつでも繰り返し視聴できるため、時間や場所に縛られず効率的に学べます。
また、新入社員の教育やスキルアップの標準化にも役立ち、講師の手間や開催費用を抑えながら質の高い研修を実現できます。
⑤SNSでの情報拡散(バイラル効果)
動画コンテンツはSNSでの情報拡散に非常に効果的です。
魅力的な動画はユーザーの共感や関心を引き、多くの人にシェアされやすくなります。
その結果、短期間でブランドや商品、サービスの認知度が大きく広がる「バイラル効果」が期待できます。
企業にとっては低コストで高い宣伝効果を得られる強力なマーケティング手段です。
動画コンテンツの事例
動画コンテンツの種類とビジネス活用事例
ここからは、動画コンテンツがどのような種類に分かれ、ビジネスでどのように活用されているかを具体例を交えて紹介します。
自社の課題や目的に合わせて参考にしやすいよう、今回は以下の4つの動画コンテンツを例にします。
- 商品・サービス紹介動画
- マニュアル・研修動画
- ブランディング動画
- 採用動画
それぞれの特徴や事例を順番に見ていきましょう。
商品・サービス紹介動画
最初の事例は商品・サービス紹介動画です。
具体的な事例として、Appleの「Meet iPhone 16」をご紹介します。
Appleの「Meet iPhone 16」は、A18チップやAI機能、Cameraボタンといったスペックを映像とナレーションで直感的に伝える好例です。
機能の使い方や導入後の体験など、サービス面の理解促進にもつながり、視聴者の共感を引き出して購買意欲を高めています。
このように、商品・サービス紹介動画は、情報を直感的に伝え、視聴者の心を動かす強力なマーケティングツールと言えるでしょう。
マニュアル・研修動画
次に紹介するのは、マニュアル・研修動画の事例です。
マニュアルや研修動画は、動画の特性を活かして業務手順や知識の習得をスムーズにし、理解と定着を促す手段として多くの企業・団体で活用されています。
具体的な事例として、Khan Academyの教育動画が参考になります。
Khan Academyは数学や科学、歴史、経済など幅広い分野を対象に、分かりやすい解説と段階的な内容構成を特徴とした動画教材を提供している非営利団体です。
この仕組みは企業研修やマニュアル動画にも応用でき、視聴者が自主的に繰り返し学習できる環境づくりに役立ちます。
ブランディング動画
次に紹介するのはブランディング動画です。
ブランディング動画は、企業の信念や世界観を直感的に伝える動画です。
具体的な事例として、メガネブランドJINSの「0円、というプライド。」という動画をご紹介します。
実際の製作現場の映像を通じて、「かけ心地の良いメガネや軽量メガネ、質感にこだわったメガネを、すべての人に納得のいく価格で届けたい」という企業の思いが描かれています。
薄型高品質レンズを追加料金なしで提供する背景にある信念が、視聴者の共感を呼ぶ好例です。
採用動画
最後にご紹介するのは、採用動画です。
企業が求職者に、自社の雰囲気や働く環境を映像で伝える動画です。
具体的な事例として、豊友工業株式会社の「社員インタビュー動画」を取り上げます。
映像では、若い女性が溶接工という職人仕事に真剣に向き合う姿が印象的に映し出されています。
「職人は男性の仕事」という先入観に対して、実際に働く女性の声が共感を呼び、採用活動に効果的な動画です。
動画コンテンツの作り方【5ステップ】
ここからは動画コンテンツの作り方を解説します。
動画コンテンツは以下の5ステップで制作されます。
- 企画・構成
- 撮影準備
- 撮影
- 編集
- 公開・配信
各ステップの注意点も交えて紹介するので、一つ一つ確認していきましょう。
ステップ1:企画・構成
動画コンテンツは、はじめに企画・構成から入ります。
動画コンテンツの成功は、企画・構成にかかっているといっても過言ではありません。
最初に、動画の目的(認知度向上、販売促進、情報提供など)とターゲット層を明確にしましょう。
次に、ターゲット層に響くテーマやメッセージを考え、動画の構成を練ります。
構成には、オープニング、本編、エンディングが含まれ、各パートで何を伝えるか、どのような映像や音楽を使うかなどを具体的に決めるようにしてください。
ここのステップで注意すべき点は以下の5点です。
- ターゲット層の興味関心を惹きつけるテーマを選ぶ
- 目的に合った構成にする
- ストーリー性を持たせる
- 視聴者が最後まで飽きない工夫をする
- 著作権・肖像権に配慮する
もしチームで動画制作する際は、目的については、何度も話し合ってブラッシュアップするのが良いでしょう。
ステップ2:撮影準備
2番目のステップは撮影準備です。
撮影準備では、必要な機材(カメラ、マイク、照明など)を揃え、撮影場所を確保します。
撮影場所の選定は、動画の内容や雰囲気に大きく影響するため、慎重に行いましょう。
また、出演者の手配や衣装の準備、撮影許可の取得なども必要に応じて行ってください。
撮影スケジュールを作成し、スムーズな撮影ができるように準備を進めます。
ここのステップで注意すべき点は以下の5点です。
- 撮影場所の選定は慎重に行う
- 必要な機材を揃える
- 出演者の手配や衣装の準備
- 撮影許可の取得
- 撮影スケジュールを作成する
撮影に際して、準備は特に重要です。
これを間違えると、余分なコストや時間がかかってしまうので、必要に応じて何度も確認するようにしてくださいね。
ステップ3:撮影
3番目のステップは撮影です。
撮影では、企画・構成で決めた内容に沿って映像を撮影します。
カメラアングルや構図、照明などを工夫し、魅力的な映像を撮影しましょう。
音声も重要なので、クリアな音声を録音できるようにマイクの位置や設定に注意してください。
ここでの注意点は以下の4点です。
- カメラアングルや構図を工夫する
- 照明を効果的に使う
- クリアな音声を録音する
- 必要なカットを撮影する
特に必要なカットだけ撮影するのは良いのですが、いくつかは余分にカットを撮影しておくと、万一の場合にも対応しやすくなるので、おすすめです。
ステップ4:編集
4番目のステップは編集になります。
編集では、編集ソフトやアプリを活用し、撮影した映像や音声を繋ぎ合わせ、不要な部分をカットし、テロップや効果音などを加えて動画を完成させます。
編集ソフトやアプリで、映像の順番や長さ、トランジション(場面転換)などを調整しましょう。
BGMや効果音を加えることで、動画の雰囲気を盛り上げることができます。
このステップでの注意点は、以下の4点です。
- 不要な部分をカットする
- テロップや効果音を加える
- BGMを選ぶ
- 動画の雰囲気に合った編集をする
上記注意点を考慮して作業するのはもちろんですが、扱う編集ソフトに関しても、自分の予算やスキルに合ったものを選ぶようにしましょう。
また、完成した動画コンテンツは、一定数の人に視聴してもらい、当初の目的に添って制作ができているかチェックしてくださいね。
ステップ5:公開・配信
最後のステップは、公開・配信になります。
完成した動画は、YouTubeやSNSなどのプラットフォームで公開・配信しましょう。
公開する際には、タイトルや説明文、タグなどを設定し、視聴者に動画を見つけやすく工夫する必要があります。
また、SNSで動画をシェアしたり、広告を出したりすることで、より多くの人に見てもらうことができるでしょう。
ここで注意すべきポイントは以下の4点です。
- タイトルや説明文、タグを設定する
- SNSで動画をシェアする
- 広告を出す
- 視聴者の反応を分析する
ここで特に重要なのは、視聴者の反応を分析することです。
最初に設定した目的が、視聴者に刺さっているか分析することで、より良い改善に繋げることができます。
改善ができれば、より多くの視聴者の心を動かし、目的を達成しやすくなるでしょう。
動画をアップしたプラットフォームによっては分析ツールが用意されていますので、有効に活用してくださいね。
動画コンテンツの主な活用プラットフォーム
動画コンテンツは、情報発信やブランディング、商品・サービスの販促など、今や幅広いビジネスで欠かせない存在です。
しかし、ただ作るだけでは十分な効果は得られません。
重要なのは「どこで活用するか」です。
本記事では、動画コンテンツの主な活用プラットフォームを以下の5つご紹介します。
- YouTube
- TikTok・InstagramなどSNS
- 自社ウェブサイト(オウンドメディア)
- Vimeoなど動画販売プラットフォーム
- オンライン学習プラットフォームでの販売
それぞれ、1つずつ確認していきましょう。
①YouTube
YouTubeは、毎月27億人以上がアクセスし、1日あたり10億時間以上の動画が視聴される巨大プラットフォームです。
この圧倒的な視聴規模を活かせば、自社の認知拡大やブランディングに大きな効果を発揮します。
Google検索との親和性も高く、動画を通じたSEO対策としても有効な手段となります。
企業の情報発信基盤として、まず押さえておきたい媒体の一つです。
②TikTok・InstagramなどSNS
TikTokやInstagramなどのSNSは、短尺動画を中心にした拡散力の高さが魅力です。
特に若年層へのアプローチに強く、トレンドや話題性を活かした動画は一気に拡散される可能性があります。
ハッシュタグやリール機能などを活用すれば、広告色を抑えつつ自然にブランドの世界観を伝えることができ、認知拡大やファン獲得につながります。
③自社ウェブサイト(オウンドメディア)
自社ウェブサイトやオンラインショップなどの「オウンドメディア」は、企業が自ら管理・運営する情報発信の場です。
ここに動画コンテンツを掲載すれば、ブランドの世界観をダイレクトに伝えられるほか、有料動画の販売や限定公開も可能になります。
収益性やコンテンツの自由度が高い一方で、集客やシステム管理、セキュリティなど自社で対応すべき課題あります。
そのため導入には計画的な運用が求められるでしょう。
④Vimeoなど動画販売プラットフォーム
Vimeoなどの動画販売プラットフォームは、高画質で広告のない環境を提供できる点が特徴です。
クリエイターや企業が有料コンテンツを配信するのに適しており、課金制やレンタル制など多様な販売モデルに対応しています。
自社サイトに埋め込むこともできるため、ブランディングを保ちながら運用可能です。
ただし、YouTubeに比べて認知拡大の面では限定的なため、目的に応じた使い分けが重要です。
⑤オンライン学習プラットフォームでの販売
オンライン学習プラットフォームでの動画コンテンツ販売とは、UdemyやTeachableなどのプラットフォーム上で、教育的な動画コンテンツを有料で提供する方法です。
視聴者は、プラットフォーム上で料金を支払い、動画講座を受講することができます。
メリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | ・学習意欲の高い人が集まる販売場所なのでターゲット層に効率的にリーチ可能 ・プラットフォームによっては集客サポートがある ・プラットフォームが学習管理機能を提供しており視聴数が上がる傾向にある |
| デメリット | ・プラットフォームに支払う手数料が発生する ・人気プラットフォームでは、多くの講座が提供されているため競争が激しい ・プラットフォーム上の販売のため、独自のブランディングが難しい場合がある |
オンライン学習プラットフォームでの販売は、教育コンテンツに特化しており、学習意欲の高いユーザーに刺さりやすい強みがあります。
一方で、手数料や競合の多さ、ブランディングの難しさなどの弱みもあるので、その点を踏まえて販売しましょう。
動画コンテンツを外部に依頼する方法
ここからは動画コンテンツを外部に依頼する方法について、どのような手段があるか説明します。
動画コンテンツの制作にはスキルと環境が必要なので、自社で製作できない場合は参考にして依頼しても良いでしょう。
外部に依頼する方法は以下の3つです。
- 動画制作会社に依頼する
- フリーランスのクリエイターに依頼する
- クラウドソーシングサービスを利用する
それぞれ具体的にどのように依頼するのか、詳しく確認していきましょう。
動画制作会社に依頼する
1つ目は動画制作会社に依頼する方法です。
各動画制作会社に直接見積もりを出してもらい、納得できたら契約します。
動画制作会社に依頼した時のメリットとデメリットは以下の表の通りです。
| メリット | ・高品質な動画制作が可能 ・時間と労力の節約 ・幅広いジャンルの動画制作に対応 ・客観的な視点やアイデアが得られる |
| デメリット | ・費用が高額になる場合がある ・コミュニケーションに手間がかかる場合がある ・納期が長くなる場合や、急な修正に対応できない場合がある |
高品質な動画制作ができるなどのメリットもありますが、一方で費用がかかるなどの難点もあるので、予算など条件を考慮して依頼するようにしましょう。
また、動画制作が依頼できる会社の例と特徴は以下の表の通りです。
| 動画制作会社 | 特徴 | 公式URL |
| Crevo株式会社 | 東京都港区にある企業で2,000社10,000件以上の制作実績があり経験豊富 | https://crevo.jp/ |
| 株式会社Global japan corporation | 業界相場の半額で成果の出る企画構成・高いデザイン性・プロの制作技術を持っている | https://gjc.me/ |
| お絵かきムービー | ストーリーを視覚的に魅力的かつ感動的に伝え、ブランドの認知度を高め、視聴者をファン化させる | https://oekaki-movie.co.jp/ |
特にお絵かきムービーについては、他社にはない手法でブランド価値を向上させたり、ファン顧客を生み出したりしてくれます。
興味がある方は、是非以下より詳細を確認してみてくださいね。
\自社商品や自社サービスをさらに販売できる!/
フリーランスのクリエイターに依頼する
2つ目はフリーランスのクリエイターに依頼する方法です。
SNSや知人などに直接依頼することになります。
主なメリットとデメリットは以下の表の通りです。
| メリット | ・比較的安価に依頼可能 ・細かい要望を伝えやすい ・納期や修正依頼など、柔軟に対応してくれる場合が多い |
| デメリット | ・人によってスキルや経験のバラツキがある ・コミュニケーションが煩雑になる可能性がある ・トラブル発生時の対応が難しい場合がある |
どうしても依頼する人に依存してしまうので、良くも悪くも当たり外れが大きいと言えるでしょう。
クラウドソーシングサービスを利用する
3つ目はクラウドソーシングサービスを利用する方法です。
動画制作依頼を行うクラウドソーシングサービスは以下があります。
- クラウドワークス
- ランサーズ
- ココナラ
他にもありますが、代表的なものとして、上記3つを抑えておけば問題ないでしょう。
この方法のメリット・デメリットは以下の表の通りです。
| メリット | ・比較的安価に依頼できる場合が多い ・多数のクリエイターから提案を受けられる ・サイトが仲介するため、金銭トラブルのリスクが低い |
| デメリット | ・提案内容の選定に時間がかかる場合がある ・クオリティによって費用にばらつきがある ・サイト利用料や手数料が発生する |
動画制作会社に比べれば費用という面では安いものの、フリーランスに直接依頼するより若干高くなる感じです。
ただ、安全性という点に関しては、クラウドソーシングサイトが仲介しているので、フリーランス直接依頼よりは高いと言えるでしょう。
動画コンテンツ制作で失敗しないための注意点
ここからは動画コンテンツ制作で失敗しないための注意点を以下3つ紹介します。
- 目的とターゲット層を明確にする
- 「作って終わり」にしない運用体制を整える
- 著作権・肖像権に配慮する
この3つは、動画コンテンツを成功させる上で欠かせないポイントです。
失敗を防ぐためにも、ひとつひとつ丁寧に確認していきましょう。
目的とターゲット層を明確にする
1つ目は、目的とターゲット層を明確にすることです。
前の事項でも触れましたが、動画制作時に目的とターゲットがしっかり定まっていないと、動画制作の方針もブレてしまい、結果的に余分な費用や時間がかかってしまうリスクがあります。
そうならないためにも、綿密に目的とターゲットを綿密な調査のうえで、明確に設定するようにしましょう。
「作って終わり」にしない運用体制を整える
動画は作って終わりではありません。
完成・公開後の効果測定こそが、成果を大きく左右します。
視聴状況やユーザーの反応を定期的に把握・分析し、内容や配信タイミングの見直しを継続的に行うことが重要です。
この一連の流れはPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)と呼ばれ、効果的な運用には欠かせません。
PDCAを円滑に回すためにも、専任チームの設置や運用体制の整備をしっかりと行いましょう。
著作権・肖像権に配慮する
最後3つ目は、著作権・肖像権に配慮する点です。
動画制作における著作権・肖像権への配慮は、法的トラブルを避けるために非常に重要です。
著作権は、音楽、映像、写真、イラスト、文章などの創作物を保護する権利です。
著作権者の許可なく、これらの創作物を動画で使用すると、著作権侵害となります。
著作権のトラブルを避ける方法としては、以下の3点を心がけましょう。
- 著作権フリーの素材を使用する
- 著作権者に使用許諾を得る
- 引用のルールを守る
肖像権は、人が自分の肖像(顔や姿)を無断で撮影・利用されない権利です。
街中で撮影した映像に偶然写り込んだ人物や、出演者の許可なく動画を使用すると、肖像権侵害となります。
肖像権のトラブルを避ける方法としては、以下の3点に留意してください。
- 出演者から事前に承諾を得る
- 街中で撮影する場合は、個人が特定できないように配慮する
- モザイク処理やボカシを入れる
著作権・肖像権は、普段から留意していれば、基本的に避けられるトラブルです。
上記内容を動画制作の際には、念頭に置いて作業を進めていってくださいね。
動画コンテンツについてよくある質問
最後に動画コンテンツについてのよくある質問を紹介します。
初心者用の質問が多いので、該当する人はしっかり確認していきましょう。
制作期間はどれくらいかかりますか?
動画制作にかかる期間は一般的に2〜3ヶ月程度が目安です。
動画の種類や長さ、完成度によって多少変動しますが、余裕を持ってスケジュールを組むことが重要です。
基本的に依頼先の制作会社による大きな差は少ないため、計画的に進めることでスムーズな制作が可能になります。
動画制作の費用相場はどれくらいですか?
以下は、動画のジャンル別費用相場をまとめた表です。
| 動画の目的 | 費用の目安(動画1本の制作費用) |
|---|---|
| YouTube(編集のみ) | 5,000〜50万円 |
| 商品・サービス紹介 | 10〜200万円以上 |
| 会社・店舗・学校紹介 | 10〜200万円以上 |
| 採用 | 10〜200万円以上 |
| セミナー・イベント | 5〜50万円以上 |
| アニメーション | 10〜300万円以上 |
| テレビCM | 100〜500万円以上 |
| 研修動画 | 5〜200万円 |
| VR動画 | 20〜550万円 |
引用:動画幹事
あくまで目安となるため、動画制作会社に依頼する際は見積もりを取りましょう。
自社の予算と照らし合わせて無理のない範囲で検討することが大切です。
動画の効果測定はどのように行いますか?
動画の効果測定は、各種プラットフォームの分析ツールを活用して行います。
YouTube動画広告の効果測定には、Google アナリティクスの活用がおすすめです。
視聴時間やエンゲージメント率をはじめ、詳細なユーザー動向も把握可能です。
Instagramのプロアカウントであれば、リーチ数やクリック数、フォロワー属性などのデータをインサイト機能で確認できます。
これらの指標を分析し、動画の改善や配信方法の最適化に役立てましょう。
YouTube以外におすすめの動画プラットフォームは?
YouTube以外にも、動画配信や販売に適したプラットフォームは複数あります。
例えば、Vimeoは高画質かつ広告なしで、クリエイターや企業によるサブスクコンテンツなどが人気です。
TikTokやInstagramは短尺動画の拡散力が高く、特に若年層へのアプローチに効果的です。
また、自社サイトやオンライン学習プラットフォームを活用すれば、直接販売やファン育成も期待できます。
目的やターゲットに応じて最適なプラットフォームを選びましょう。
まとめ
本記事では、動画コンテンツの基本や作り方から活用法・配信先などを解説してきました。
本記事のまとめは以下の4点です。
- 動画コンテンツとは、映像と音声で構成されたデジタルコンテンツである
- 企業が動画コンテンツを利用する事で、ブランディング・認知度向上のメリットがある
- 動画コンテンツの配信プラットフォームは、主に5種類ある
- 動画コンテンツ制作で失敗しないためには、動画公開後の効果測定が大切
動画コンテンツは戦略的に制作・運用することで、ビジネスに大きな価値をもたらします。
今回ご紹介したポイントを押さえ、目的に合った活用を心がけましょう。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/