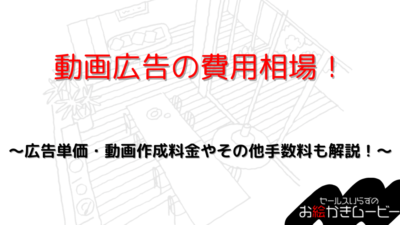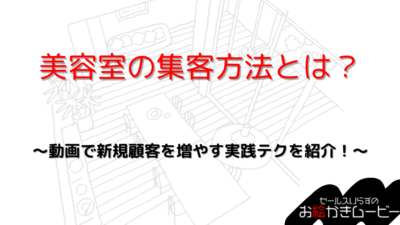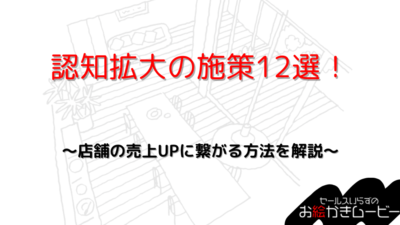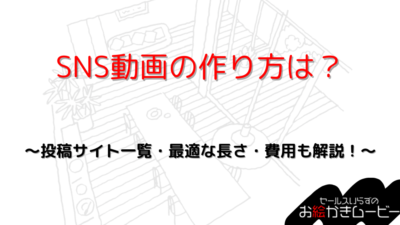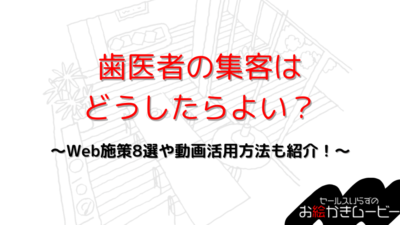イベント動画で成功へ!効果的な活用法と制作ガイド
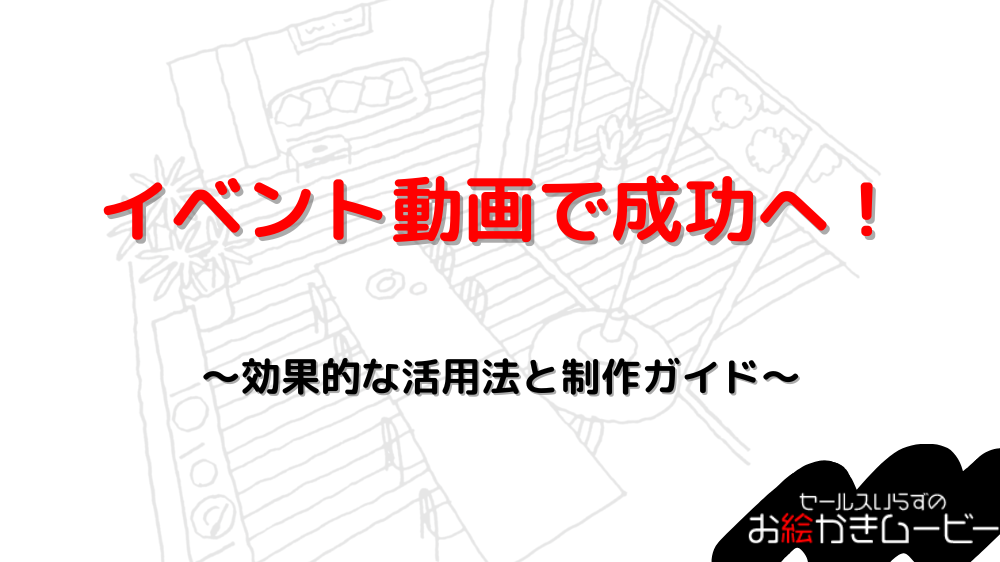
イベントは企業と顧客が直接繋がることができる、貴重な機会です。
そしてそれを撮影した「イベント動画」は、単なる記録映像ではありません。
次回の集客、企業の信頼性向上、そして参加できなかった層へのアプローチを実現する、強力なマーケティング資産です。
本記事ではイベント動画の効果的な活用法や、動画の企画・制作段階で意識すべきコツ、具体的な活用方法まで解説していきます。
ぜひ本記事を参考に、イベント動画を最大限に活用してください。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/
なぜ今、イベント動画が重要なのか?3つの効果と活用シーン
イベント動画とは、企業や団体が開催するイベントやセミナー、社員総会などで使われる映像コンテンツのことです。
そもそも、なぜ今イベント動画が重要とされているのでしょうか。
本記事ではその理由を、以下の2つに分けて解説していきます。
- イベントの成果を最大化する3つの効果
- 【時系列で解説】イベント動画の種類と活用シーン
それぞれ、1つずつ確認していきましょう。
イベントの成果を最大化する3つの効果
イベント動画を制作・活用することで、以下の3つの効果が期待できます。
| ①次期イベントへの集客に利用可能 ②企業の認知度向上 ③圧倒的な情報量を届けられる |
イベント動画は、イベントの熱狂や感動の様子を凝縮して伝えることで、不参加だった層の「次回は参加したい」という強い意欲を喚起し、次期集客に繋げます。
また、SNSやYouTubeを通じて広く配信することで、企業やブランドの認知度を一気に高めることが可能です。
さらにイベントの詳細や出演者の情報など、短時間で効率的に伝えることができます。
【時系列で解説】イベント動画の種類と活用シーン
イベント動画は、【開催前・中・後】の時系列に沿って使い分けることで、最大の効果を発揮します。
イベント動画の種類と活用シーンについて、以下にまとめました。
| 活用タイミング | 動画の種類 | 目的 | 活用シーン |
|---|---|---|---|
| イベント前 | ティザー動画(告知動画) | ・期待感の醸成 ・イベント参加への関心喚起 ・早期申し込みの促進 | ・イベント内容の一部を先行公開 ・参加への期待感を高め集客を促進など |
| イベント中 | アタック動画 | ・インパクトを与える ・注意を向ける | ・イベントの節目のタイミング ・社員総会やキックオフ・表彰式など |
| イベント後 | イベントレポート動画 | ・次期集客 ・ブランディング | ・SNSでハイライト動画を公開 ・営業時の資料として活用など |
告知から開催後の見込み客育成まで、各フェーズに適した動画を活用することで、イベントの効果を最大化することが可能です。
成果を出す!イベント動画制作で押さえるべき3つのポイント
イベント動画を制作しても、「なんだかパッとしない」「思ったほど活用できない」と悩む担当者は少なくありません。
本記事では、イベント動画を確実にビジネスの成果に変えるために、動画制作で押さえるべき以下の3つの重要ポイントを解説します。
- ポイント1:目的の明確化(KPI設定)
- ポイント2:ターゲットに「響く」メッセージの設計
- ポイント3:視聴者の心を掴む構成と演出
それでは、1つずつ見ていきましょう。
ポイント1:目的の明確化(KPI設定)
イベント動画をビジネス成果に繋げるためには、まず目的を明確にし、達成すべきKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。
例えば「次期イベントの申し込みを20%増やす」「企業サイトのアクセスを30%増やす」「YouTubeチャンネルの登録者を1,000人増やす」など、具体的な数値を設定します。
また、数値を具体的に設定する事で、動画の効果も測定しやすくなります。
KPIを明確にすることで、動画制作や配信の方向性が定まり、成果を最大化できるでしょう。
ポイント2:ターゲットに「響く」メッセージの設計
イベント動画の効果を高めるためには、ターゲット層に響くメッセージを設計することが重要です。
例えば、若年層をターゲットにするなら、トレンドやエンタメ要素を取り入れ、視覚的にインパクトのある内容にすると効果的でしょう。
一方、ターゲットがビジネスマン向けの場合は、参加することで得られる具体的なビジネス成果を強調するのがおすすめです。
ターゲットが求める「メリット」や「解決策」をしっかり理解し、それを伝える心に響くストーリーやメッセージを作ることが成功のポイントです。
ポイント3:視聴者の心を掴む構成と演出
イベント動画の成功には、視聴者の心を引きつける構成と演出が欠かせません。
動画の冒頭3秒~で、最も感動的あるいは重要なシーンを提示し、視聴者の興味を一気に引きつけましょう。
会場の熱気や参加者の楽しんでいる表情を挿入するのも、おすすめです。
また、場面転換のスピードやBGMも、動画の印象を大きく左右します。
最後まで飽きさせないテンポの良さと、感動を増幅させる質の高い演出が重要です。
【目的別】すぐに使えるイベント動画の構成テンプレート
イベント動画の構成は視聴者の関心を引き、印象に残る内容を伝えるための重要な要素です。
本記事では、イベント動画を作成するための構成テンプレートを、以下の3つご紹介します。
- 集客力を高める「イベント告知・ティザー動画」
- イベントの価値を伝える「イベント紹介・ブランディング動画」
- 次回の参加に繋げる「イベントレポート・ダイジェスト動画」
それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。
集客力を高める「イベント告知・ティザー動画」
この動画の最大の役割は、開催前の段階で見込み客の期待感を最高潮に高め、イベントへの集客を最大化することです。
具体的な制作は、以下の構成テンプレートで進めましょう。
| 構成 | 内容 |
|---|---|
| 興味を引くオープニング | ・インパクトのある映像や音楽で視聴者の注意を引く |
| イベントの概要紹介 | ・イベントのテーマや目的を簡単に紹介 ・主要な登壇者やゲストにも触れる |
| 期待感を高めるシーン | ・「今年も必見の内容!」など、視聴者に参加したいと思わせる言葉を強調 ・過去のイベント映像なども取り込む |
| 参加方法の案内 | ・参加方法や申し込みページへの誘導 ・早期予約で特典あり!など参加を促すメッセージを入れる |
| エンディング | ・企業ロゴやSNSアカウント、イベント用ハッシュタグを表示 |
この表を活用すれば、イベント告知・ティザー動画の構成を視覚的に整理しながら作成することができます。
イベントの価値を伝える「イベント紹介・ブランディング動画」
この動画の役割は、企業やイベントの持つ理念、社会的意義といった「目に見えない価値」を伝達し、ブランドイメージを高めることにあります。
具体的な制作は、以下の構成テンプレートで進めましょう。
| 構成 | 内容 |
|---|---|
| 興味を引くオープニング | ・インパクトのある映像や音楽で視聴者の注意を引く |
| 企業・ブランド紹介 | ・企業の理念やビジョンを短く紹介 ・ブランドの強みや特徴を伝える |
| イベント内容の紹介 | ・イベントの目的やテーマを簡潔に説明 ・イベントの見どころやハイライトを紹介 |
| 参加者の声・感想 | ・実際に参加した人々のインタビューや感想を挿入 ・参加者が得たメリットや感動を強調 |
| イベントの成果・影響 | ・イベントがもたらした結果や影響を伝える ・成功事例や具体的な数字を挙げて説得力を持たせる |
| エンディング | ・企業ロゴやスローガンを再度表示 |
ぜひこのテンプレートを参考に、イベント紹介・ブランディング動画を制作してみてください。
次回の参加に繋げる「イベントレポート・ダイジェスト動画」
この動画の目的は、イベント後の熱気をビジネス成果に繋げることです。
参加者には満足感を再確認させ、不参加者には「次回は参加したい」という強い意欲を引き起こします。
具体的な制作は、以下の構成テンプレートで進めましょう。
| 構成 | 内容 |
|---|---|
| 興味を引くオープニング | ・インパクトのある映像や音楽で視聴者の注意を引く |
| イベントの概要紹介 | ・イベント名、開催日時、場所、テーマなどの基本情報を簡潔に紹介 |
| イベントのハイライト | ・イベントの重要な瞬間をダイジェストで紹介 ・視覚的に魅力的なシーンを強調 |
| 参加者の反応・インタビュー | ・参加者の感想やインタビューを挿入 ・感動的な反応や印象に残った瞬間をピックアップ |
| イベントの舞台裏 | ・イベント準備の舞台裏など普段見られないシーンを紹介 |
| エンディング | ・企業ロゴやスローガン ・SNSリンク ・次回イベントの詳細情報などを表示 |
この構成を活用し、次回の参加に繋げる「イベントレポート・ダイジェスト動画」を魅力的に制作しましょう。
イベント動画の作り方と費用相場【外注vs自作】
イベント動画は高い効果が期待できる反面、「制作にどれくらいの費用がかかるのか」「自社で作るべきか、プロに頼むべきか」という疑問がつきものです。
本記事ではイベント動画の作り方と費用相場について、以下の4つに分けて解説していきます。
- 制作会社(外注)に依頼する場合
- 自作(インハウス)する場合
- 外注と自作のメリット・デメリットを比較
- 【重要】失敗しない制作会社・イベント企画会社の選び方
それでは、1つずつ見ていきましょう。
制作会社(外注)に依頼する場合
イベント動画の制作を外注する最大のメリットは、高品質な仕上がりと専門性の高い企画力を得られる点です。
しかし、成功させるためには以下の点に注意が必要です。
| 注意点 |
|---|
| ①費用相場を把握 ②納期の厳守 |
イベントの規模や撮影日数などによって変動しますが、一般的なイベント動画の費用相場は平均すると10万円〜80万円程度とされています。
依頼時にこちらの予算を明確に提示しましょう。
予算が分かれば、制作会社は最適な撮影・編集プランを提案しやすくなります。
また納期が曖昧な業者は、納品の遅れや料金説明の不透明さなど、リスクが伴います。
納期や見積もり、規約の説明が明確な信頼できる制作会社を選びましょう。
自作(インハウス)する場合
イベント動画を自作(インハウス)する最大のメリットは、費用を大幅に抑えられることです。
しかし機材が用意できていない場合は、カメラや三脚・照明機材などを自分で用意しなければなりません。
カメラの価格はピンキリですが、10万円程度〜50万円程度が一般的です。
機材が揃っている場合は、数万円あれば動画制作をスタートできます。
ただし、品質については以下の2点に注意が必要です。
| 注意点 |
|---|
| ①メッセージの明確化 ②編集とBGMでインパクトを出す |
「何を伝えたいか」というメッセージや、動画のコンセプトを制作前に徹底的に明確にしましょう。
これがブレると、伝えたいことが伝わらない動画になってしまいます。
また、編集スキルが動画の品質を左右します。
映像が間延びしないよう、BGMや効果音を効果的に使い、テンポ良く仕上げてください。
テキストを端的に挿入するなど、視覚的な工夫で視聴者を惹きつけるのが重要です。
外注と自作のメリット・デメリットを比較
イベント動画を自作する場合と外注する場合の、メリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット/デメリット | 外注 | 自作 |
|---|---|---|
| メリット | ・高品質な動画を制作できる ・自社業務に集中できる ・最新の編集ソフトを使用してくれる | ・制作するメンバーとの意思疎通が簡単 ・費用を抑えられる |
| デメリット | ・費用が高い ・業者の見極めが大変 | ・撮影機材を用意しなければならない ・社員が作業の時間を取られる |
外注の場合は、自社業務に集中できるうえに、クオリティの高い動画制作を期待できます。
しかし、費用を高く取られたり、悪徳業者に依頼してしまい納期に間に合わなかったりする可能性があるので、じっくり業者の比較検討をして依頼をしましょう。
自作の場合は、費用を抑えられる点が大きなメリットです。
しかし、撮影機材を自分で用意したり、自分たちで編集をしたりするので、手間がかかるというデメリットもあります。
自社の経営状況をもとに、メリットとデメリットを考慮して、自作するか外注するかを決めましょう。
【重要】失敗しない制作会社・イベント企画会社の選び方
イベント動画や映像制作を外注する際に、失敗しない制作会社・イベント企画会社の選び方は、主に以下の4つです。
| 注意点 |
|---|
| ①実績と専門性 ②企画力と提案力 ③透明性と信頼性 ④担当者とのコミュニケーション |
自社の業界やイベント種類の制作経験が、豊富にあるかを確認してください。
また、単に指示通りではなく「どう活用するか」まで踏み込んだ戦略的な提案をしてくれるか、確認が必要です。
見積もりや納期・規約の説明が明確で、料金体系が分かりやすい会社を選びましょう。
さらに、担当者と円滑にコミュニケーションが取れるかも重要です。
話しやすさや、レスポンスの速さなど総合的に判断してください。
よくある質問
ここからは、よくある質問を以下の6つに分けて解説します。
- イベント動画の適切な長さは?
- イベント動画の制作期間はどれくらい?
- SNSで効果的に拡散させるコツは?
- イベント動画の著作権・肖像権は?
- 効果的なイベント動画の活用方法は?
- 制作費用を抑える方法はありますか?
それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。
イベント動画の適切な長さは?
イベント動画の長さは、イベントの目的や掲載媒体の種類、視聴者の世代などによって異なりますが、60秒〜3分程度が妥当といえるでしょう。
実際のイベント動画をご紹介します。
お絵描きムービーでは、紹介動画・案内動画は3分程度で制作されています。
YouTubeであれば長尺で見る方も多いので、数分から数十分の動画を制作しても問題ありません。
一方、Instagramのショート動画やTikTokで視聴する方は1分以内に納めると、視聴してもらいやすくなります。
媒体ごとに適切な動画の尺は変わるので、どの媒体に動画を載せるかあらかじめ決めるようにしましょう。
イベント動画の制作期間はどれくらい?
イベント動画の制作期間は、平均すると1ヶ月〜2ヶ月程度かかるとされています。
具体的には以下の通りです。
| 動画のジャンル | 制作期間 |
|---|---|
| 配信用動画 | 2週間程度 |
| セミナー動画 | 1ヶ月程度 |
| 大規模イベント | 1.5ヶ月程度 |
制作作業の中でも、特に編集作業は動画の長さやこだわり具合によって、作業時間が大きく変動します。
なお、動画の種類や目的、メッセージ、予算を明確にしておくと、動画制作がスムーズに進むので、制作期間を短くしたい方は依頼前に準備しておくとよいでしょう。
SNSで効果的に拡散させるコツは?
SNSで効果的に拡散させるコツは、「投稿する動画の尺」と「インパクト」にあります。
長尺のイベントレポート動画をそのまま投稿するのではなく、魅力的なハイライトシーンをショート動画に切り抜きましょう。
SNSでは、冒頭3秒で視聴者の足を止めるインパクトのあるシーンを配置し、続きは本編(YouTubeなど)へ誘導します。
また、トレンドのBGMやハッシュタグを活用することで、アルゴリズムによるインプレッションを最大化し、自然な拡散を促進できます。
イベント動画の著作権・肖像権は?
イベント動画の著作権は基本的に、制作会社に帰属します。
しかし、会社によっては依頼側に著作権が帰属するケースもあるので、契約書等でしっかり確認しましょう。
自作の場合は、企業のロゴや建物など、思いがけず著作権を侵害するものが映り込んでいるケースもあります。
撮影中・編集中、そして公開直前に動画を一通り見て、著作権侵害がないか確認しましょう。
肖像権は有名人にも与えられる権利です。
モデルなどを動画に起用する場合は、「肖像権使用許諾同意書」を取得し、肖像権を侵さないように気をつけましょう。
肖像権や著作権を無視すると法的トラブルにつながる可能性があるため、慎重に対応するのが大切です。
効果的なイベント動画の活用方法は?
イベント動画は、以下の場面で活用できます。
- イベントの告知やPR
- 集客
- 社内研修
- 採用活動
主催者からのメッセージを入れたり、クイズ形式で視聴者が参加できる動画にしたりすると、イベントの盛り上がりを手助けしてくれるでしょう。
また複雑な説明が必要な場合などに利用すると、イベントをスムーズに進められるのでおすすめです。
制作費用を抑える方法はありますか?
動画制作費用を抑える方法は、主に以下の3つです。
| ①動画の目的を明確にする ②撮影日数を減らす ③素材を再利用する |
「誰に何を伝え、どう行動してほしいか」という目的を絞ることで、撮影すべきシーンや編集の工数を最小限に抑えられます。
また、制作費用の中で大きな割合を占める人件費や機材費は、撮影日数に比例します。
スケジュールを最適化することで、大幅なコストダウンが可能です。
さらなるコストダウンのためには、過去のイベント映像、企業紹介動画、または自社で撮影した写真素材などを積極的に活用しましょう。
新規撮影の量を減らすことで、撮影にかかる時間だけでなく、編集にかかる手間と費用も抑えることができます。
まとめ
本記事ではイベント動画の効果的な活用法や、動画の企画・制作段階で意識すべきコツなどを解説してきました。
本記事をまとめると以下の3点になります。
- イベント動画を制作・活用することで「企業の認知度の向上」が期待できる
- イベント動画はイベント終了後も、集客に活用可能
- SNSで効果的に拡散させるコツは、トレンドのBGMやハッシュタグを活用すること
ぜひ、本記事で紹介した方法を実践して、イベント動画を最大限に活用してみてください。
認知度向上や集客の効果を実感できるはずです。
次回のイベントをさらに成功させるための一歩として、ぜひ取り入れてみましょう!
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/