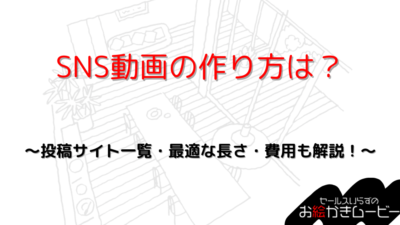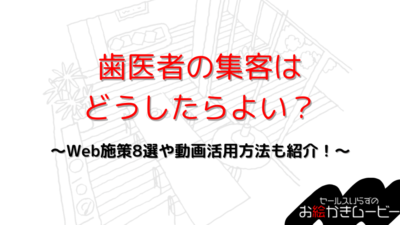認知拡大の施策12選!店舗の売上UPに繋がる方法を解説
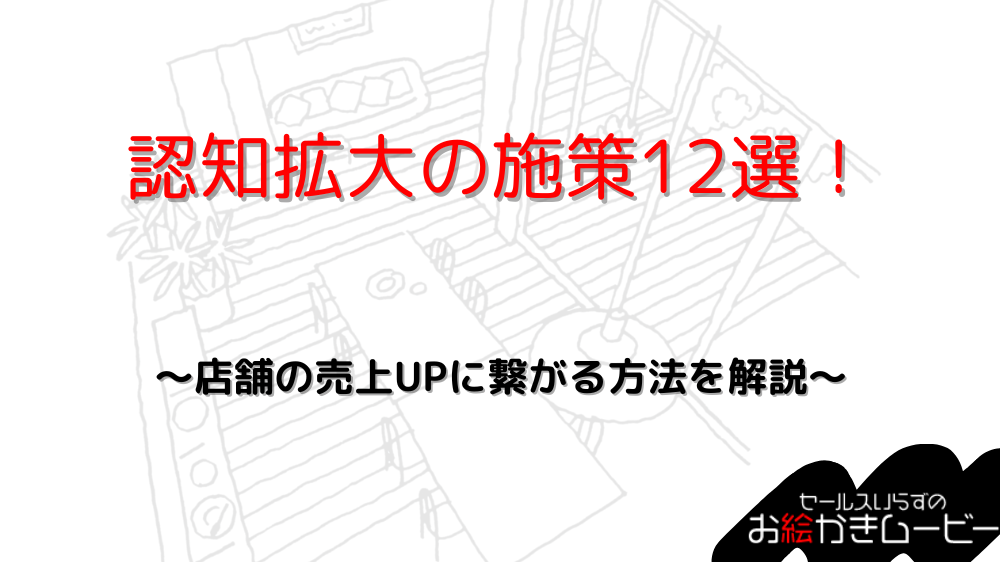
「こだわりの商品やサービスには自信があるのに、なぜか客足が伸びない」
「お店の良ささえ伝われば、もっと売上が上がるはずなのに」
そんなもどかしさを感じている店舗経営者様は、決して少なくありません。
商品やサービスがどれほど素晴らしい価値を持っていても、それがお客様に届いていなければ、存在していないのと同じになってしまいます。
現状を打破し、売上を右肩上がりに導くために欠かせないものが 「認知拡大」 です。
本記事では、店舗経営においてなぜ認知拡大が最優先事項なのかを改めて整理しつつ、すぐに実践できる具体的な施策12選を厳選して、分かりやすく解説します。
具体的には、主に以下の通りです。
- 認知拡大とは?施策を知る前の基礎知識
- 【オンライン施策】低コストで始められる認知拡大の方法
- 【オフライン施策】地域に根差した認知拡大の方法
- 自店舗の認知度が低い原因とは
本記事の施策を活用し、認知拡大のための導線を整えていきましょう。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/
認知拡大とは?施策を知る前の基礎知識
認知拡大の施策を理解する前に、まずは基本を押さえておきましょう。
ここでは、認知拡大の意味や考え方、混同されやすい用語の違い、そして店舗経営における重要性について、以下の3つの視点から解説します。
- 認知拡大とは「知ってもらう」ための全ての活動
- 意外と知らない「認知度」と「知名度」の違い
- なぜ今、店舗の売上アップに認知拡大が重要なのか
それでは、1つずつ確認していきましょう。
認知拡大とは「知ってもらう」ための全ての活動
認知拡大とは、文字通り「自社の店舗、商品、サービスをターゲット顧客に広く知ってもらうための全ての活動」を指します。
単に店名を知ってもらうだけでなく、以下のようにお店の「中身」までを正しく理解してもらうことを目指します。
- どこにあるのか?(場所)
- 何を売っているのか?(商品・サービス)
- どんな特徴や強みがあるのか?(コンセプト・価値)
- 誰のための店なのか?(ターゲット)
お客様が何かを必要としたとき、「あのお店に行ってみよう」「あの商品を買ってみよう」と、自店舗を思い出してもらうための土台作りが認知拡大です。
意外と知らない「認知度」と「知名度」の違い
「認知度」と「知名度」は混同されがちですが、マーケティングの世界では明確に使い分けられます。
この違いを理解することが、目標設定において非常に重要です。
知名度と認知度の違いは以下表の通りです。
| 項目 | 知名度 (Name Recognition) | 認知度 (Awareness) |
|---|---|---|
| 意味 | 「名前を聞いたことがある」というレベル | 「何をしているか、どんな価値があるか」を理解しているレベル |
| 顧客の理解度 | 浅い | 深い |
| ゴール | 名前を覚えてもらうこと | 商品やサービスの購入・利用を検討してもらうこと |
| 例 | 「〇〇カフェという名前は聞いたことがある」 | 「〇〇カフェは、落ち着いた雰囲気でこだわりのコーヒーが飲めるお店だ」 |
知名度が高いだけでは、売上には直結しにくいのが現実です。
私たちが目指すべきは、単なる知名度アップではなく、ターゲット顧客に対する「認知度」を高め、お客様の心を動かすレベルでの理解を広げることが、認知拡大の真の目的となります。
なぜ今、店舗の売上アップに認知拡大が重要なのか
現代において、店舗の認知拡大がかつてないほど重要になっている背景には、主に3つの理由があります。
- 競合の増加と市場の成熟
- 消費者の購買行動の変化
- 新規顧客獲得コストの上昇
あらゆる業種で競合が増え、お客様は無数の選択肢の中からお店を選びます。
品質や価格だけでは差別化が難しくなり、「なぜこのお店を選ぶべきなのか」という理由を明確に伝え、存在を知ってもらわなければ、そもそも選択の土俵に上がることすらできません。
また、インターネットとスマートフォンの普及により、お客様は来店前に念入りに情報収集をするのが当たり前になりました。
つまり、オンライン上に自店舗の情報が存在しなければ、お客様にとっては「存在しない」のと同じことになってしまうのです。
さらに、新規顧客を一人獲得するためのコストは上昇傾向にあります。
だからこそ、まずは自店舗の価値を正しく理解してくれる可能性の高いターゲット層に狙いを定め、効率的にアプローチする「認知拡大」が不可欠です。
将来の「ファン」や「リピーター」になり得る層に知ってもらうことで、長期的な売上安定に繋がります。
これらの理由から、認知拡大はもはや「やれたら良い」施策ではなく、店舗が生き残り、成長していくための「必須戦略」と言えるでしょう。
【オンライン施策】低コストで始められる認知拡大の方法
インターネットを活用した認知拡大は、比較的低コストで始めやすいのが特徴です。
まずは、多くの店舗がすぐに始めやすいオンラインでの認知拡大施策を6つご紹介します。
以下に詳細をまとめました。
【オンライン施策】認知拡大施策一覧
| 施策内容 | 特徴 | コスト | 施策のしやすさ |
|---|---|---|---|
| Googleビジネスプロフィール | ・地図検索・ローカル検索に強い ・来店につながりやすい | 無料 | 簡単 |
| Instagram・X運用 | ・ビジュアル重視 ・店舗の雰囲気を伝えやすい | 無料 | 手軽 |
| 地域メディア・ポータル掲載 | ・地元ユーザーにまとめて認知してもらえる | 50万~500万以上 (サイトの規模やページ数によって変動) | やや難しい |
| プレスリリース配信 | ・メディア掲載による信頼性が強い ・拡散力が高い | 3万円~15万円前後 (配信サイトによって変動) | やや難しい |
| インフルエンサー施策 | ・影響力のある人の発信 ・一気に信頼と認知を獲得 | フォロワー単価×フォロワー数で計算 (単価相場2~4円前後) | 難しい |
| note・ブログ記事 | ・悩み解決型で検索流入を狙える | 基本無料 | やや難しい |
それでは、1つずつ確認していきましょう。
Googleビジネスプロフィールで地図に表示させる
最も優先度が高く、無料でできる最強の認知拡大施策が「Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)」の活用です。
お客様が「近くのカフェ」「〇〇駅 ラーメン」などとGoogle検索やGoogleマップで検索した際に、自店舗の情報を表示させることができます。
具体的には以下の点を実施しましょう。
- オーナー登録を済ませる
- 情報を正確かつ詳細に入力する
- 魅力的な写真をたくさん投稿する
- 口コミを集め、丁寧に返信する
- 「最新情報」機能を活用する
この方法は、来店意欲が非常に高いユーザーに直接アプローチできる極めて効果的な方法です。
地図に表示させた後も、お客様に飽きられないように、できるだけこまめに情報を更新してくださいね。
InstagramやXで商品やお店の魅力を発信する
SNSは、お店のファンを作り、お客様と直接コミュニケーションを取ることができる強力なツールです。
特にビジュアルが重視されるInstagramや、情報の拡散力が高いX(旧Twitter)は、店舗の認知拡大に欠かせません。
InstagramやX(旧Twitter)にもそれぞれ特徴があり、相性の良い業種があります。
詳細は以下表の通りです。
| SNS | 特徴 | 相性の良い業種 |
|---|---|---|
| ・写真や動画がメイン ・ビジュアルでの訴求力が高い ・ハッシュタグ検索が主流 ・20代~40代の女性利用者が多い | ・飲食店 ・美容室 ・アパレル ・雑貨店 ・ネイルサロン など | |
| X (Twitter) | ・リアルタイム性と拡散力が高い ・短いテキストでのコミュニケーション ・キャンペーンなどとの相性が良い ・幅広い年齢層、趣味のコミュニティ | ・飲食店(限定メニュー告知) ・書店(新刊情報) ・イベント告知 など |
具体的なアクションプランは、以下の通りです。
- プロフィールを充実させる
- ターゲットに響く投稿を継続する
- ハッシュタグを戦略的に活用する
- コミュニケーションを大切にする
SNSは、昨今どの業種であっても活用が欠かせません。
まだSNSを開設していない場合は、早急に開設を行うことをおすすめします。
地域メディアやポータルサイトに情報を掲載する
特定の地域に特化したWebメディアやポータルサイトへの情報掲載も、地域密着型の店舗にとっては非常に有効です。
ここで行うべき、具体的な内容は以下の通りです。
- 自店舗のエリアの地域メディアを探す
- 無料掲載と有料掲載を検討する
- 掲載情報を常に最新に保つ
各地域のローカルニュースサイトなどは、「自分の街の新しいお店を探したい」という目的意識の高いユーザーが見ているため、来店に繋がりやすいというメリットがあります。
プレスリリースでメディア掲載のチャンスを狙う
プレスリリースとは、テレビ、新聞、雑誌、Webメディアといった報道関係者に向けて、自店舗の新しい情報を公式に発表する文書のことです。
メディアに取り上げられれば、広告費をかけずに非常に大きな認知拡大効果が期待できます。
プレスリリースのネタになる情報例は以下の通りです。
- 新店舗のオープン
- 画期的な新商品の発売
- 地域貢献活動や社会貢献活動
- ユニークなイベントの開催
- 調査データの発表(例:〇〇に関するアンケート調査結果)
- 周年記念キャンペーン
具体的なアクションプランは以下の通りです。
- プレスリリース配信サービスを利用する
- メディアが取り上げたくなる切り口を考える
- 魅力的なタイトルと写真を用意する
「PR TIMES」や「@Press」といった配信サービスを利用すれば、多くのメディアに一括で情報を届けられます。
ただ、注目してもらうために、ニュースとしての価値を意識した内容にすることが重要です。
そのため、一目で内容が分かり、興味を引くタイトルと、質の高い写真を用意するようにしましょう。
インフルエンサーに商品やサービスを体験してもらう
インフルエンサーマーケティングと言われる方法です。
特定分野で影響力を持つ人物(インフルエンサー)に商品やサービスを体験してもらい、その感想をSNSなどで発信してもらいます。
具体的なアクションプランは以下の通りです。
- 自店舗と親和性の高いインフルエンサーを探す
- 依頼方法を検討する
- 正直な感想を投稿してもらう
- ステマ規制を遵守する
インフルエンサーマーケティングは、広告特有の売り込み感が少なく、フォロワーからの信頼性が高いため、共感を呼びやすく、高い認知拡大効果や購買促進効果が期待できます。
noteやブログで「ユーザーの悩み」に答える記事を書く
noteやブログで「ユーザーの悩み」に答える記事を書くことは、認知拡大に効果的な施策のひとつです。
例えば、以下のようなテーマの記事が挙げられます。
| 項目 |
|---|
| ①飲食店→初めて来店する人の不安を解消する記事 (例:一人でも入りやすい時間帯、注文の流れ、混雑しやすい時間) ②美容室→メニュー選びに迷う人向けの記事 (例:カット・カラー・パーマの違い、髪質別のおすすめメニュー) ③整体院→セルフケアを紹介する記事 (例:自宅でできるストレッチや姿勢改善のポイント) |
こうした「役立つ情報」の蓄積は、検索エンジンからの流入を増やすだけでなく、読者からの「この店は信頼できる」という安心感に繋がります。
一度書いた記事はネット上の資産として、24時間365日あなたに代わって集客し続けてくれる心強い味方になるはずです。
【オフライン施策】地域に根差した認知拡大の方法
オンライン施策に加えて、地域密着型の店舗ではオフラインでの認知拡大も欠かせません。
本記事では地域ですぐに取り組みやすい、オフラインでの認知拡大施策を5つご紹介します。
以下に詳細をまとめました。
【オフライン施策】認知拡大施策一覧
| 施策 | 特徴 | コスト | 施策のしやすさ |
|---|---|---|---|
| チラシのポスティング・新聞折込 | ・地域住民に直接情報を届けられる | ・折り込みチラシ (3~5円程度/1部) ・ポスティング (4~8円程度/1部) | やや難しい (制作・配布の手間がかかる) |
| 近隣店舗とのコラボレーション | ・新たな客層に相互でアプローチできる | ・基本無料か安い | 手軽 |
| 看板・のぼりの見直し | ・通行人への視認性が高く即効性がある | ・無料 | 手軽 |
| 地域フリーペーパー・情報誌 | ・地元に関心の高い層へ届けやすい | ・A4サイズ/1P (50万~80万) ・1/2サイズ/1P (30万~40万) ※サイズによって料金が変動 | 難しい (掲載枠の選定が必要なため) |
| 公共施設・自治体の掲示板 | ・信頼性が高く地域密着型の認知が可能 | ・数万円~ (自治体によって異なる) | 簡単 (許可申請などの手間はある) |
それでは、1つずつ確認していきましょう。
チラシのポスティングや新聞折込で直接届ける
デジタル時代においても、チラシや新聞折込といった紙媒体は、特定のエリアに確実に情報を届けられる強力な手段です。
特に、PCやスマートフォンをあまり利用しない高齢者層へのアプローチや、商圏が限定される地域密着型店舗には非常に有効です。
具体的なアクションプランは以下の通りになります。
- ターゲットに響くデザインを心がける
- 配布エリアとタイミングを戦略的に決める
何を伝えたいのか(例:オープン記念、割引セール)が一目で分かるキャッチコピーを配置し、魅力的な商品の写真を大きく使うのが重要です。
また、商圏分析を行い、ターゲット顧客が多く住むエリアに絞って配布したり、週末の来店を促したいなら「〇曜日の何時」など配布のタイミングを考慮したりしましょう。
地域のイベントに出展して直接交流する
地域のお祭り、マルシェ、フリーマーケットなどのイベントに出展することは、潜在顧客と直接顔を合わせ、お店の魅力や商品のこだわりを伝えられる絶好の機会です。
イベント出展のメリットは以下の通りです。
- 直接的なコミュニケーション
- 体験の提供
- 潜在顧客へのリーチ
直接のコミュニケーションや体験が地域のイベントに出展の大きなメリットと言えます。
ここの具体的なアクションプランは以下の通りです。
- 出展するイベントをリサーチする
- 目を引くブース作りを工夫する
- 実店舗への来店を促す仕組みを作る
ここで重要な点は、お店のコンセプトと客層が合うイベントを選ぶことです。
事前にしっかりリサーチして、イベントを選ぶようにしましょう。
近隣店舗とのコラボレーションで新たな客層に届ける
業種は違えど、ターゲット顧客が近い近隣のお店と協力することで、お互いの顧客を紹介し合い、新たな客層にアプローチできます。
単独で施策を行うよりも、相乗効果で大きな認知拡大が期待できます。
コラボレーションのアイデア例としては以下の通りです。
- カフェ × 書店: カフェのレシートを書店に持っていくと割引、書店のブックカバーをカフェで見せるとドリンクサイズアップなど
- 美容室 × アパレルショップ: お互いのショップカードやチラシを店頭に設置(相互送客)
- 飲食店 × 農家: 地元農家の野菜を使った限定メニューを提供し、お互いのお店やSNSで紹介し合う
具体的なアクションプランは以下の通りです。
- コラボ相手を探す
- Win-Winの関係を築く
- 共同で告知を行う
ここでの重要なポイントは、コラボ相手との信頼関係になります。
お互い利益が出るように信頼関係をしっかり構築して、コラボを行うようにしましょう。
看板やのぼりを見直して通行人の目を引く
お店の前を通りかかる人々にとって、看板やのぼりは最初の接点です。
これらが魅力的でなければ、せっかくの潜在顧客を逃していることになります。
今一度、お店の外観を見直してみましょう。
見直しのチェックポイントは以下の通りです。
- 視認性
- 分かりやすさ
- 魅力
- 清潔感と状態
上記の点について、実際に少し離れた場所から歩いてみて、自分のお店がどう見えるか客観的にチェックしましょう。
看板に情報を詰め込みすぎず、最も伝えたいメッセージ(例:「名物〇〇」「ランチやってます」)に絞れているかも確認してみてください。
また、可能ならA型看板(スタンド看板)を活用しても良いでしょう。
地域のフリーペーパーや情報誌を活用する
地域の家庭や事業所に無料で配布されるフリーペーパーや情報誌も、根強い影響力を持つメディアです。
新聞折込と同様に、特定のエリアの住民に広く情報を届けられますし、広告掲載だけでなく編集企画で取り上げてもらうチャンスもあるでしょう。
地域のフリーペーパーや情報誌を活用するためのアクションアイテムは以下の通りです。
- 地域の情報誌をリサーチする
- 広告出稿を検討する
- 情報提供(プレスリリース)を行う
店舗を構えている地域で良さそうなフリーペーパーや情報誌があれば、上記手順で活用していってください。
公共施設や自治体の「掲示板」にポスターを掲示する
公共施設や自治体の掲示板にポスターを掲示する方法は、地域住民に自然な形で店舗を知ってもらえる認知拡大施策です。
人の出入りが多く、信頼性の高い場所に掲示されるため、安心感を持って見てもらいやすい点が特徴です。
掲示場所の例としては、以下のような施設が挙げられます。
| 項目 |
|---|
| ①市役所・区役所などの行政施設 ②図書館や公民館、地域センター ③児童館や子育て支援施設 |
掲示には申請やルールがある場合が多いものの、比較的低コストで始められます。
店舗情報やキャンペーン内容を簡潔にまとめ、来店のきっかけづくりとして活用すると効果的です。
【注目施策】動画を活用した認知拡大プロモーション
近年、スマートフォンの高速通信化に伴い、動画コンテンツの視聴が日常的になりました。
動画は、静止画やテキストに比べて圧倒的に多くの情報を伝えることができ、認知拡大の非常に強力な武器となります。
動画が認知拡大に効果的な3つの理由
動画が認知拡大に効果的な3つの理由は以下の通りです。
- 圧倒的な情報量
- 感情に訴えかけやすい
- 記憶に残りやすい
1分間の動画が伝える情報量は、Webページ3,600ページ分に相当すると言われ、圧倒的です。
また、ストーリー性のある映像やBGMは、視聴者の感情に直接訴えかけ、共感や親近感を生み出しやすいという特徴もあります。
さらに映像と音声によって、お店の雰囲気、商品の質感、スタッフの人柄などを、テキストや写真だけでは伝えきれないレベルでリアルに届けることができ、お客様の記憶に残りやすいです。
お店の魅力を伝えるショート動画の活用方法
TikTokやInstagramリール、YouTubeショートといった1分程度の短い動画は、現代のユーザーに非常に好まれており、認知拡大の入り口として最適と言えます。
ポイントは「完璧さ」よりも「リアルさ」と「継続」 です。
スマートフォン一つで気軽に撮影・編集可能です。
まずは週に1〜2本でも良いので、継続的に発信してみましょう。
オーナーの人柄や想いを伝えるコンセプト動画
ショート動画で興味を持ってもらった後に、より深くお店のことを知ってもらい、ファンになってもらうために有効なのが、3〜5分程度のコンセプト動画です。
これは、お店のウェブサイトやYouTubeチャンネルのトップに掲載することを想定した、いわば「お店の顔」となる動画です。
コンセプト動画では、以下の内容を伝えるようにしましょう。
- 創業のきっかけやストーリー
- お店のコンセプトや大切にしている価値観
- 商品やサービスへのこだわり
- オーナーやスタッフの想い、お客様へのメッセージ
オーナー自身の言葉で情熱を語ることで、単なる「お店」から、ストーリーと想いを持った「共感できる存在」へと昇華させることができます。
これは、価格競争に巻き込まれない強力なブランディングとなり、長期的に愛されるお店作りに繋がるでしょう。
動画制作に自信がなければ、「お絵かきムービー」など、動画制作を外部に依頼しても良いでしょう。
認知拡大施策の事例から学ぶ
ここでは、具体的な成功事例を4つ紹介します。
自店舗の状況と照らし合わせながら、施策のヒントを見つけてください。
【SNS活用】株式会社土屋鞄製造所
ランドセル作りから始まった老舗の鞄メーカーである土屋鞄製造所は、SNS、特にInstagramを活用して高いブランド価値と熱心なファンを獲得している代表例です。

引用:TSUCHIYA KABAN™ 公式サイト — 土屋鞄製造所
本記事で判断した施策のポイントは以下の通りです。
- 徹底した世界観の構築とビジュアル訴求
- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の積極的な活用
- 製品の裏側にある「物語」の発信
土屋鞄のInstagramは、単なる商品カタログではありません。
プロのカメラマンが撮影したような高品質な写真で、製品が使われる日常のワンシーンを切り取り、温かみのある世界観を構築しています。
企業が広告費をかけずに、ファンによるリアルな口コミを拡散させる非常に優れたサイクルも注目すべきポイントです。
「#土屋鞄」や「#私の土屋鞄」といったハッシュタグを検索すると、多くの愛用者が自慢の鞄を投稿しているのがわかります。
同社はこれらの投稿を公式アカウントのストーリーズで紹介することがあり、ユーザーにとっては「自分の投稿が公式に認められた」という喜びとブランドへの愛着に繋がります。
また、工房での製造風景や、職人の手仕事、製品開発に込められた想いなどを丁寧に発信しています。
これにより、消費者は製品を単なる「モノ」としてではなく、作り手の顔が見える「物語のある作品」として認識するようになります。
このストーリーテリングが、価格競争に陥らない強力な付加価値となっているのです。
【ファンイベント活用事例】株式会社ヤッホーブルーイング
「よなよなエール」などのクラフトビールで有名なヤッホーブルーイングは、顧客を「ファン」として扱い、熱狂的なコミュニティを形成する「ファンマーケティング」の第一人者です。

その中核をなすのが、オンラインと連携したオフラインイベントです。
「よなよなエールの超宴」と名付けた数千人規模の大規模なファンイベントを毎年開催しています。
そこでは、ただビールを飲むだけでなく、ブルワー(醸造家)によるセミナー、ファン同士の交流を促す企画、スタッフとファンが一体となって盛り上がるコンテンツが多数用意されています。
この「非日常的な体験」こそが、ブランドへの忠誠心を飛躍的に高めるのです。
イベントは一過性のもので終わらせず、日頃からSNSや公式ECサイトのコンテンツを通じてファンとの接点を持ち続けています。
イベントで生まれた熱量をオンラインで維持・拡散し、次のイベントへの期待感を高めるという見事な連携がなされていると言えるでしょう。
【動画・コンテンツ活用事例】株式会社クラシコム(北欧、暮らしの道具店)
ECサイト「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコムは、YouTubeを軸としたコンテンツマーケティングによって、多くのファンを魅了し続けています。

引用:北欧、暮らしの道具店
その手法は、もはやECサイトの枠を超え、一つのメディアカンパニーと言えるほど巧みです
北欧、暮らしの道具店のYouTubeには直接的な商品説明動画はほとんどありません。
人気コンテンツは、モーニングルーティンや休日の過ごし方(Vlog)、人生への考え方、料理レシピなど、ターゲット顧客の「暮らし」に寄り添うものばかりです。
まず徹底的に役立つ情報や共感できるコンテンツを提供し、その世界観に触れた視聴者が、結果的にサイトを訪れ商品を購入するという流れを確立しています。
また、各動画の概要欄には、動画内で登場した商品や関連するコラム記事へのリンクが丁寧に設置されており、視聴者が興味を持った瞬間にスムーズに購入や情報収集へ移行できる設計になっています。
【ホワイトボードアニメーション活用事例】株式会社三輪山勝製麺
伝統ある製麺技術のこだわりを伝えるため、三輪山勝製麺はお絵かきムービーの「ホワイトボードアニメーション」を活用しました。
手描きでイラストが描かれていく過程を見せるこの手法は、視聴者の目を引きやすく、複雑な製造工程や歴史を最後まで楽しく視聴させることに成功しています。

引用:一筋縄 三輪山勝製麺
この施策のポイントは、単なるCMではなく「物語」として情報を届けた点です。
物語の中では、品質へのこだわりゆえに価格が高くなり、当初は卸売業者から敬遠された苦悩も正直に描かれました。
そうした背景を包み隠さず伝えることで、視聴者は商品だけでなく企業の姿勢や想いに共感し、信頼感を抱きやすくなります。
文章や写真だけでは伝わりにくい想いや背景をストーリーとして可視化したことが、ブランドへの深い理解を生み、結果として認知拡大につながった好例といえるでしょう。
施策の前に立てるべき認知拡大の基本戦略
ここまで様々な施策を紹介してきましたが、やみくもに手を出しても効果は半減してしまいます。
施策を実行する前に、まずは自店舗の「認知拡大戦略」の土台を固めることが成功への近道です。
誰に知ってもらいたいか(ターゲットの明確化)
最も重要なのが、「誰に」情報を届けたいのかを明確にすることです。
「すべての人」に届けようとすると、メッセージがぼやけてしまい、結局「誰にも」響きません。
ターゲットを明確にするには、具体的に描く「ペルソナ設定」を行うのがおすすめです。
ペルソナとは、自店舗にとって最も理想的な顧客像を、以下のように実在する人物かのように詳細に設定したものです。
- 基本情報: 年齢、性別、居住地、職業、年収
- ライフスタイル: 趣味、休日の過ごし方、よく見る雑誌やWebサイト
- 価値観・悩み: どんなことに価値を感じるか、どんなことで悩んでいるか
一つ例を挙げると以下のようになります。
| 例:郊外のオーガニックカフェのペルソナ |
|---|
| 田中さきさん、32歳、女性。都内に通勤する会社員。夫と子供(3歳)の3人暮らし。健康や食の安全に関心が高く、休日は家族で公園に行ったり、少し質の良い食材で料理を楽しんだりするのが好き。SNSはInstagramをよく見る。 |
ここまで具体的に設定することで、「さきさんなら、どんな情報に興味を持つだろう?」「どんな言葉なら響くだろう?」 と、相手の目線に立った情報発信ができるようになるでしょう。
お店の何を一番に伝えたいか(強みの再確認)
次に、設定したターゲットに対して、自店舗の「何を」一番に伝えたいのか、つまり独自の強みを再確認します。
「うちの強みは〇〇です」と即答できない場合は、以下の3C分析フレームワークで整理してみましょう。
3C分析の3Cとは、以下の点を指します。
- Customer(顧客): ターゲット顧客は、何を求めているか?
- Competitor(競合): 周辺の競合店は、どんな強みを持っているか?
- Company(自社): 自店舗の強みは何か?
この3つの視点から、「競合は提供しておらず、かつ顧客が求めている、自社だけの価値」 を見つけ出しましょう。
ここで考えた「強み」こそが、認知拡大施策を通じて一貫して伝え続けるべきメッセージの核となります。
将来的な顧客を意識する(潜在層へのアプローチ)
認知拡大に取り組む際は、すぐに来店・購入する顕在層だけでなく、将来的に顧客になる可能性がある潜在層を意識することが重要です。
潜在層とは、まだ自社の商品やサービスを知らない、もしくは必要性に気づいていない人たちを指します。
この段階では売り込みよりも、「知ってもらう」「覚えてもらう」ことを優先しましょう。
役立つ情報発信や共感を生むストーリーを通じて接点を作ることで、必要になったタイミングで思い出してもらいやすくなります。
こうした積み重ねが、将来的な集客や売上につながってくるのです。
どの状態を目指すのか(目標とゴール設定)
最後に、認知拡大施策を通じて「どの状態を目指すのか」という具体的な目標(ゴール)を設定します。
目標がなければ、施策の成果を正しく評価し、改善していくことができません。
以下のSMARTの法則 を用いて、具体的で測定可能な目標を立てましょう。
- S (Specific): 具体的に
- M (Measurable): 測定可能か
- A (Achievable): 達成可能か
- R (Relevant): 関連性があるか
- T (Time-bound): 期限があるか
上記を踏まえた良い目標例と悪い目標例は以下表の通りです。
| 良い目標例 | 悪い目標例 |
|---|---|
| 3ヶ月後までに、Instagramのフォロワーを1,000人増やし、プロフィールからのウェブサイトクリック数を月間50件にする | インスタを頑張って、お客さんを増やす |
具体的な期限と目標数値を設定するのがコツです。
そして、最終的なゴール(KGI: Key Goal Indicator)が「売上〇%アップ」のように設定したら、その達成度を測るための中間指標(KPI: Key Performance Indicator)として、以下のような項目を設定します。
- Googleビジネスプロフィールの表示回数、ルート検索数
- SNSのフォロワー数、エンゲージメント率
- ウェブサイトへのアクセス数
- チラシからのクーポン利用数
これらの数値を定期的にチェックすることで、施策が順調に進んでいるか、改善が必要かを判断できます。
もしかして?自店舗の認知度が低い原因とは
様々な施策を試しているのに、なかなか効果が出ない…。その場合、施策のやり方以前に、根本的な原因が潜んでいる可能性があります。
発信している情報がターゲットに合っていない
最もよくある失敗が、前述の「ターゲット設定」が曖昧なまま、独りよがりな情報発信をしてしまっているケースです。
例えば、30代の健康志向の女性をターゲットにしているカフェが、若者向けの派手なスイーツやボリューム満点のランチばかり発信していては、本来届けたい層には響きません。
対策としては、もう一度ペルソナに立ち返り、「その人は本当にこの情報を喜ぶか?」という視点で、発信する内容や言葉遣い、写真のテイストを見直しましょう。
情報発信の量や頻度が不足している
認知拡大は、一度やれば終わりではありません。
情報が次々と流れていく現代では、継続的な発信が不可欠です。
以下のような状態では、お客様の信頼を得ることは難しく、アルゴリズム的にも不利になります。
- Instagramアカウントは作ったけれど、投稿は1ヶ月前で止まっている
- Googleビジネスプロフィールの情報がオープン当初のまま など
このような場合、無理のない範囲で、更新頻度の目標を決めましょう。
「SNSは週に3回投稿する」「Googleビジネスプロフィールは月に1回、最新情報を投稿する」など、ルーティン化することが継続のコツです。
他のお店との違いや魅力が伝わっていない
お客様は、「なぜ数あるお店の中から、あなたのお店を選ぶべきなのか」という理由を探しています。
その理由、つまり「自店舗ならではの強み」が明確に伝わっていなければ、お客様の心には残りません。
「こだわりの食材を使っています」「アットホームな雰囲気です」といった表現は、多くのお店が使っており、具体性に欠けます。
「誰の、どんな悩みを、どのように解決できるのか」という顧客にとっての価値(ベネフィット)を伝えることを意識しましょう。
- 悪い例: 「こだわりのコーヒー豆」
- 良い例: 「仕事で疲れたあなたが、心からリラックスできる一杯。バリスタが厳選したスペシャルティコーヒーです」
このように、強みを顧客目線の言葉に変換することで、魅力が格段に伝わりやすくなります。
よくある質問
最後に、店舗経営者からのよくある質問を紹介します。
認知拡大の施策にはどれくらいの費用がかかりますか?
無料で始められるものから、数十万円以上かかるものまで様々です。
予算に合わせて無理なく始め、費用対効果(ROI)を検証するのが重要になります。
まずはGoogleビジネスプロフィールやSNSなど、無料で効果の高い施策から着手するのがおすすめです。
施策の効果はどれくらいの期間で現れますか?
施策によって大きく異なります。
認知拡大は、基本的に時間がかかるものです。
特にファン作りやブランディングは、一朝一夕にはいきません。
短期的な成果が出なくても焦らず、中長期的な視点でコツコツと継続することが重要です。
一人で店舗運営をしていて時間がありません
限られた時間の中で成果を出すには、「優先順位付け」と「効率化」が鍵です。
どうしても時間がない場合は、まずは最も費用対効果が高いと考えられる「Googleビジネスプロフィールの最適化」に絞って取り組みましょう。
他にもSNSの投稿は、予約投稿ツールを使えば空き時間にまとめて作成できます。
チラシのデザインは、「Canva」などの無料ツールを使えば、テンプレートを活用して簡単に作成可能です。
どうしても手が回らない部分は、専門家や代行サービスに外注するのも一つの選択肢になるでしょう。
どの施策から始めるのがおすすめですか?
まずは「Googleビジネスプロフィール」の整備から始めることを強く推奨します。
なぜなら、来店意欲の高いユーザーに直接アプローチでき、無料で始められる最も基本的な施策だからです。
マーケティングという言葉が難しく感じます
難しく考える必要はありません。
マーケティングとは、突き詰めれば「お客様に自店舗を知ってもらい、好きになってもらい、来店して喜んでもらうための一連の工夫」です。
「どうすればお客様は喜んでくれるだろう?」と、お客様の顔を思い浮かべながら考えること、その全てがマーケティング活動の第一歩です。
この記事で紹介した施策も、お客様とのコミュニケーションを円滑にするための「道具」にすぎません。
ぜひ、楽しみながら取り組んでみてください。
まとめ
本記事では、認知拡大の施策(12種類)や、店舗の売上UPに繋がる方法などを解説してきました。
本記事をまとめると以下の3点です。
- 認知拡大とは自社の店舗、商品、サービスをターゲット顧客に広く知ってもらうための全ての活動
- 動画は圧倒的な情報量で認知拡大に効果的
- 認知拡大に取り組む際は来的に顧客になる可能性がある潜在層を意識する
認知拡大は、「知ってもらう」「覚えてもらう」を積み重ねていく取り組みです。
本記事で紹介した施策の中から、自店舗に合うものを無理のない形で実践してみてください。
また、商品やサービスの魅力や想いを分かりやすく伝えたい場合には、お絵かきムービーの活用も効果的です。
文章だけでは伝えきれない価値を物語として届け、認知拡大を後押しします。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/