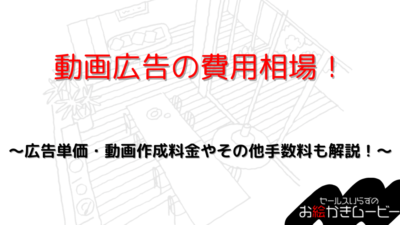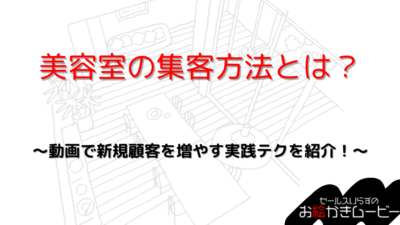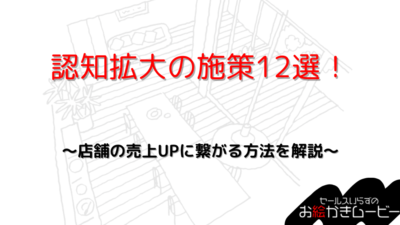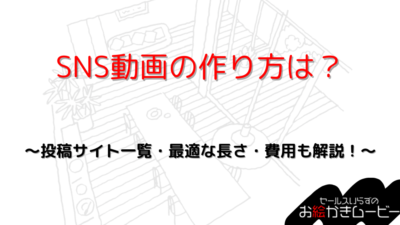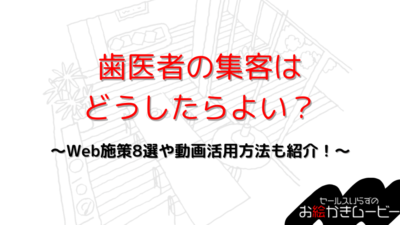認知拡大の方法とは?飲食店におすすめの動画マーケティングを解説!
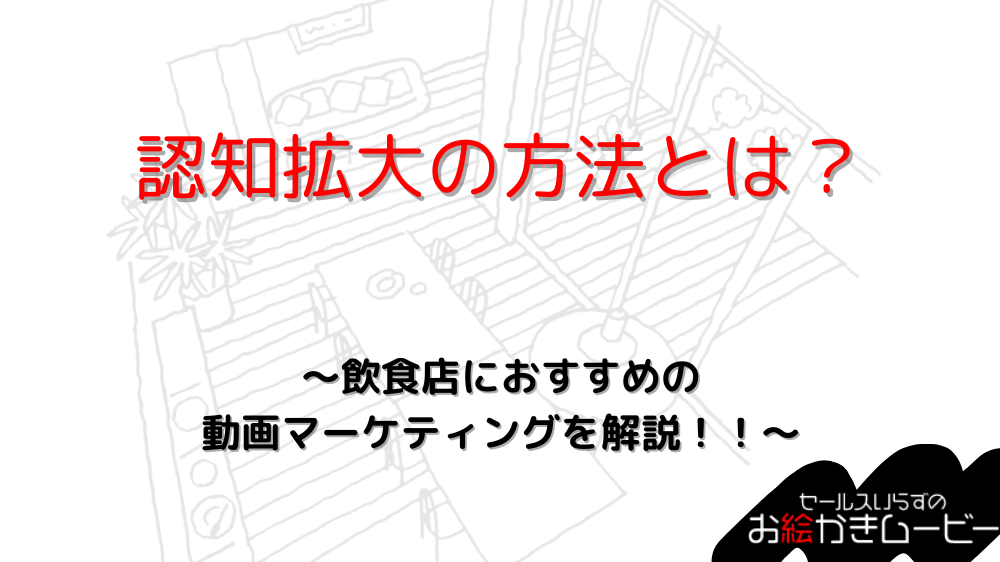
「もっと多くの人に自分の店を知ってほしい」と感じても、「なかなか自店の魅力を伝えきれない」と悩みを抱える飲食店は少なくありません。
特に競合が多い地域では、メニューやサービスだけでは差別化も難しいですよね。
そこで本記事では認知拡大の方法として「動画マーケティング」をおすすめします。
動画マーケティングとは、動画を使って自分の店の魅力を発信するマーケティング手法の1つです。
本記事では認知拡大の方法や、メリット、動画の活用法などを解説していきます。
ぜひ参考にして下さい。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/
そもそも認知拡大とは?基本を解説
そもそも認知拡大とは、どのような状態を言うのでしょうか。
本記事では認知拡大の基本について、以下の5つに分けて解説していきます。
- 認知度と知名度の違いとは?
- なぜ今、お店の認知度が低いのか
- マーケティングにおける認知段階
- 効果的な認知拡大戦略の立て方
- より多くの人に知ってもらう方法の基本
それぞれ、1つずつ確認していきましょう。
認知度と知名度の違いとは?
「認知度」と「知名度」はどちらも日常で耳にする言葉ですよね。
同じ様な意味に感じるかもしれませんが、少し違います。
2つの違いを、分かりやすく表にまとめてみました。
| 項目 | 知名度 | 認知度 |
|---|---|---|
| 状態 | 名前を知っている状態 | 中身や価値まで理解している状態 |
| 深さ | 浅く広く知られている | 深く理解されている |
| 例文 | 「○○って聞いたことあるけど、顔が思い出せない」 | 「○○の認知度を全国で調査した」 |
細かいですが、違いを知っておくといいでしょう。
なぜ今、お店の認知度が低いのか
お店の認知が低い理由は様々ですが、主に以下のことが考えられます。
- 競争の激化と情報量の多さ
- 消費者行動の変化
お店の認知度が低いのは、競合が増えて存在が目立ちにくくなっていることがあげられます。
また物価高の影響などで外食をする人が少なくなり、外に出なくなったことでお店の存在に気が付くことがなくなったことも考えられるでしょう。
このような消費者行動の変化も、飲食店の認知度低下の一因です。
マーケティングにおける認知段階
マーケティングにおける「認知」は、商品やサービスを顧客に「知ってもらう」ための重要な初期段階です。
この段階の目的は、自社の存在をターゲット顧客の意識の中に位置づけ、その後の興味・関心・欲求・行動へと繋げることです。
具体的には、広告、SNS、広報活動などを通じて、顧客が「あ、こんな商品があるんだ」と気づくきっかけを作ります。
この「気づき」が、顧客が比較検討を始めたり、情報を調べたりする第一歩となります。
この段階で、いかに効率的に、そして多くの人々にアプローチできるかが、その後の成果を大きく左右します。
効果的な認知拡大戦略の立て方
効果的な認知拡大には、まず「誰に知ってもらいたいか」というターゲットの明確化が不可欠です。
次に、ターゲットが普段利用するメディアやプラットフォームを特定します。
例えば、若年層がターゲットならTikTokやInstagram、ビジネス層ならFacebookなどが効果的です。
プラットフォームを選定したら、それぞれの特性に合わせたコンテンツを制作します。
動画でも記事でも、顧客の興味を引く形で情報を発信しましょう。
最後に、これらの活動を一貫して行い、PDCAサイクルを回しながら改善を続けることが重要です。
より多くの人に知ってもらう方法の基本
ターゲットに「刺さる」発信を続けることで、より深い認知へと繋がります。
より多くの人に知ってもらうには、顧客の視点に立ち「どう行動したいのか」「何に興味があるか」を考えることが出発点です。
まず、WebサイトやSNSといった「オンライン」での情報発信を強化しましょう。
ターゲットがよく使うプラットフォームで、役立つ情報や共感を呼ぶコンテンツを定期的に発信することで、自然と人々の目に留まる機会が増えます。
次に、「オフライン」でも接点を作ります。
イベント出展や地域コミュニティへの参加、口コミを促進する仕組み作りなどが有効です。
飲食店が動画で認知拡大するメリット
飲食店が動画で認知拡大をするメリットには、どのようなものがあるでしょうか。
本記事ではそのメリットを、以下の3つご紹介します。
- お店の雰囲気やこだわりが伝わる
- 料理のシズル感をリアルに届けられる
- 他の認知施策との違いと効果
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
お店の雰囲気やこだわりが伝わる
動画は、写真や文字だけでは伝えきれないお店の魅力を、五感に訴えかける形で表現できます。
たとえば、スタッフの活気ある接客や、店内のBGM、照明の反射まで、リアルな空気感を伝えることが可能です。
これにより、お客様は来店前から期待感を膨らませ、「行ってみたい!」という気持ちを高めます。
料理のシズル感をリアルに届けられる
「シズル感」とは、料理の音や香り、湯気などから伝わる「おいしそう!」という臨場感のことです。
たとえば、肉を焼くジュージュー音や、揚げ物のサクッという音、食材から立ち上る湯気などがそれにあたります。
動画は、このシズル感を最も効果的に伝えることが可能です。
静止画では表現できない瞬間をリアルに届けることで、見る人の食欲を強く刺激します。
これにより「おいしそうだから行ってみよう!」という来店動機を、直接的に生み出すことが可能になります。
他の認知施策との違いと効果
動画は他の認知施策(看板、チラシ、写真など)と比べて、短時間で多くの情報を伝えることができます。
写真や文字では料理の見た目や、店の場所は伝えられます。
しかし雰囲気や調理の音、スタッフの表情など来店につながる要素を伝えるには限界があります。
忙しいオーナー向け動画活用の始め方
忙しい飲食店オーナーにとって、動画制作は難しそうでハードルが高いと思われがちですよね。
しかし必要なのは、今や高性能なカメラ機能を備えたスマートフォン1台です。
スマホを三脚に固定するだけで、手ブレのない安定した映像が撮れます。
また、アプリを使えば、無料でプロのような編集が可能です。
特別なスキルがなくても、料理の調理工程や完成した料理を美しく撮影し、テロップやBGMを追加するだけで、魅力的な動画が簡単に作れます。
無料で使えるおすすめ編集アプリ
動画編集と聞くと、専門的な知識や高価なソフトが必要だと考えがちですが、現在はスマートフォンで手軽にプロ並みの編集ができるアプリが多数あります。
飲食店オーナーにおすすめなのは、直感的な操作で初心者でも使いやすい以下のアプリです。
これらのアプリを使いこなせば、スキマ時間にスマホでサッと動画を作り、お店の魅力を発信することができます。
1日15分でできる動画作成のコツ
忙しいオーナーでも動画作りを継続するためのコツは、完璧を目指さず、毎日のルーティンに組み込むことです。
1. テーマを絞る
「今日のおすすめメニュー」や「調理のワンポイント」など、テーマを一つに絞りましょう。
毎日違うテーマを探す必要がなくなり、撮影が楽になります。
2. 隙間時間を活用する
仕込みの合間や開店前の15分など、店の業務で発生する「ついで」の時間を活用します。
わざわざ動画撮影のために時間を取るのではなく、日常業務の延長として捉えましょう。
3. 短尺動画に特化する
InstagramのリールやTikTokのような短い動画に絞って作れば、撮影から編集までを短時間で終えられます。
情報過多な現代において、短い動画は最後まで見てもらいやすいというメリットもあります。
どのSNSで発信?プラットフォーム選び
実際SNSで動画発信をする際、たくさんあるプラットフォームの中から、どこを選べばいいのでしょうか。
本記事では、プラットフォーム選びについて、以下の3つに分けて解説していきます。
- インスタグラムのリール活用術
- TikTokのショート動画で拡散を狙う
- YouTubeショートでファンを育成
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
インスタグラムのリール活用術
インスタグラムの「リール」は、15秒から90秒の短い動画を投稿する機能です。
アルゴリズムの仕様変更により、フォロワー外のユーザーにも動画を積極的に表示するようになりました。
そのためフォロワーが少なくても、一気に多くの人に見てもらえるチャンスがあります。
リールを活用する際は「音」と「最初の5秒」が鍵となります。
トレンドのBGMや効果音を使うことで、ユーザーの興味を引き、動画を最後まで見てもらう確率が高まります。
また、冒頭で「これを見れば○○がわかる」といったインパクトのある一言を入れ、見る人の心を掴む工夫をしましょう。
TikTokのショート動画で拡散を狙う
TikTokは短尺動画に特化したSNSで、特に若年層に圧倒的な人気を誇ります。
その最大の特徴は、独自のアルゴリズムによって、フォロワー数に関係なく動画が「おすすめ」として多くのユーザーに表示されやすい点です。
これにより、動画一本で爆発的な拡散(バズ)を狙うことが可能です。
TikTokで効果的に認知を広げるには、「流行」と「エンターテイメント性」を意識してください。
流行の音楽やダンス、チャレンジ企画などを取り入れることで、動画が共有されやすくなります。
また、料理の工程を早送りで見せたり、スタッフのユニークな日常を切り取ったりするなど、見ていて楽しい動画作りを心がけることも、拡散の鍵となります。
YouTubeショートでファンを育成
YouTubeショートは、YouTubeの広大なユーザー基盤を活用できる短尺動画機能です。
TikTokやリールと同様、スマートフォンで手軽に制作・視聴できるフォーマットです。
特にエンゲージメントの高い視聴者と、関係を構築するのに適しています。
YouTubeショートの強みは、通常のYouTube動画との連携です。
ショート動画で視聴者の興味を引きつけ、「続きは本編で」と誘導することで、チャンネル登録者の増加に繋げることができます。
例えば、料理のハイライトシーンをショートで公開し、レシピの詳細を通常の長い動画で解説するといった使い方が効果的です。
これにより、単なる認知拡大に留まらず、深いファンコミュニティの育成に貢献します。
お客様が来店したくなる動画アイデア集
お店の魅力を伝え、お客様に「行ってみたい!」と思わせるきっかけとして、動画は非常に効果があります。
しかし実際に、どのような動画だとお客様が来店したくなるでしょうか。
本記事では、お客様が来店したくなる動画アイデア集として、以下の5つに分けて解説していきます。
- 調理風景のタイムラプス動画
- 看板メニューの紹介動画
- スタッフの自己紹介・Q&A動画
- 店内のこだわり紹介ツアー
- 期間限定メニューやイベントの告知
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
調理風景のタイムラプス動画
調理風景のタイムラプス動画は、お客様の好奇心と期待感を掻き立てる効果的なコンテンツです。
数時間かかる仕込みや調理の過程を数秒から数十秒に凝縮することで、まるでマジックのように見せることができます。
例えば、パン生地がふっくらと膨らむ様子、何層も重ねてケーキを作る繊細な作業などを撮影します。
普段、あまり目にすることのないシーンを動画で共有することで、料理へのこだわりや職人技を視覚的に訴えることが可能です。
これにより、料理が完成するまでの過程への興味が湧き、実際にその料理を食べてみたいという気持ちを高められます。
看板メニューの紹介動画
お店の看板メニューは、動画で最も魅力を伝えやすい題材です。
ただ完成した料理を映すだけでなく、お客様が「食べたい!」と感じる瞬間を切り取って動画にしましょう。
たとえば、肉を焼く際のジューシーな音、熱々のチーズがとろける様子、盛り付けの美しさなど、五感に訴えかける「シズル感」を強調します。
さらに、そのメニューに使われているこだわりの食材や、調理工程の裏側を少しだけ見せることで、お客様の期待感をさらに高めることができます。
動画を通じて「このメニューを食べるために、お店に行きたい」と思わせるようなコンテンツ作りが重要です。
店内のこだわり紹介ツアー
動画は、お店の雰囲気を伝える上で効果的なツールです。
ただ写真で店内を映すだけでなく、お店のコンセプトやこだわりをオーナー自らが紹介する「店内ツアー」動画は、お客様に強い印象を残します。
たとえば、内装に使われている木材の種類や、壁に飾られたアート作品に込められたストーリーを語ることで、お店の世界観を深く伝えられます。
また、カウンター席から見える景色や、個室の特別感を強調すれば、「特別な日に利用したい」と思ってもらえるきっかけになります。
動画を通じてお店の空間にストーリーを持たせることで、お客様は来店前から「その空間を体験したい」という気持ちになります。
期間限定メニューやイベントの告知
期間限定メニューやイベントは、動画と非常に相性の良いコンテンツです。
文字や写真だけでは伝わりにくい「特別感」を、動画なら効果的に演出できます。
たとえば、季節限定の食材を使ったメニューの調理風景を動画で見せることで、その料理が食べられる貴重な時期であることを強調できます。
また、イベントの雰囲気を事前に動画で紹介することで、「楽しそうだから行ってみよう」とお客様の参加意欲も上がるはずです。
メニューの販売開始日やイベントの開催日を明確に示し、お客様に「今行かないと!」と思わせるような緊急性を持たせることで、来店を促すことができます。
動画以外の認知拡大プロモーション事例
ブランドやお店の魅力を伝える方法は、動画だけではありません。
本記事では、動画以外の認知拡大プロモーション事例として、以下の3つをご紹介します。
- 地域メディアやインフルエンサー活用
- MEO対策でGoogleマップから集客
- 知広告の活用事例とポイント
それぞれ、1つずつ確認していきましょう。
地域メディアやインフルエンサー活用
動画以外にも、地域に根差したメディアやインフルエンサーを活用することで、効率的に認知を拡大できます。
地域メディアでは、地元のフリーペーパーや情報誌、コミュニティFMなどで紹介してもらうことで、特定の地域に住む層に直接アプローチできます。
特に、お店のオープンや新サービスの告知は、地元の人々の関心を引きやすいでしょう。
また、インフルエンサーのとの連携も有効です。
強い影響力を持つインフルエンサーに商品やサービスを体験してもらい、SNSで発信してもらいましょう。
ターゲット層に認知拡大が期待できます。
MEO対策でGoogleマップから集客
MEO(Map Engine Optimization)対策は、Googleマップ上での検索順位を上げるための施策です。
特に店舗ビジネスにとって、Googleマップからの集客は非常になってきます。
対策の基本は、Googleビジネスプロフィールの充実です。
お店の最新情報(営業時間、電話番号、住所など)を正確に入力するのはもちろん、メニューや店内の写真を多数掲載します。
また、お客様からの口コミは順位に大きく影響するため、積極的にお願いし、丁寧に返信しましょう。
これらの対策を継続することで、Googleマップ上での露出が増え、来店意欲の高いユーザーを効率よく集客できます。
認知広告の活用事例とポイント
認知広告は、単に多くの人に見てもらうだけでなく、その後の購買行動に繋げるための戦略的なアプローチが重要です。
本記事では認知広告の成功事例としてJA全農新潟の「新潟茶豆 たくさん食べてご馳走を当てようキャンペーン」の広告をご紹介します。

引用:JA全農にいがた「新潟茶豆 たくさん食べてご馳走を当てようキャンペーン」
こちらはレシートによる応募方式により、消費者が対象商品を実際に購入する動機付けになりました。
また、LINE・メール・はがきの3種類に対応しており、幅広い世代が参加しやすい設計となっており、成功例といっていいでしょう。
認知の拡大と販売を後押しした、成功例といっていいでしょう。
認知施策の効果測定とKPI設定
認知度を向上させるためのマーケティング活動は、単に多くの人に知ってもらうだけでなく、その効果を数値で測ることが重要です。
そこで本記事では、認知自作の効果測定とKPI設定について、以下の3つに分けて解説していきます。
- 認知広告のKPI設定方法
- SNSでの認知度の測定方法
- 効果測定に基づいた改善の進め方
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
認知広告のKPI設定方法
認知広告は自社の製品やサービスの認知を広めるための広告です。
KPIは組織が掲げる目標を達成するために、その進捗度合いを測るためのものです。
例えば、「売上を上げる」という大きな目標に対し、「新規顧客を100人獲得する」といった具体的な目標がKPIです。
以下の3つの主要な指標を抑えましょう。
| 指標名 | 意味 | 測定方法 |
|---|---|---|
| ブランド認知度 | ・ブランドを知っているかを示す指標 | ・検索エンジンで測定 ・アンケートなど |
| リーチ数 | ・広告が届いたユーザーの数 | ・各分析ツール |
| エンゲージメント | ・広告に対するユーザーの反応 | ・「いいね」「コメント」「シェア」の数 ・アンケートなど |
認知広告の効果を最大化するには、感覚に頼るのではなく、適切なKPIを設定して効果を測定することが不可欠です。
これらの指標を総合的に分析することで、広告が目標達成にどの程度貢献したかを正確に把握できます。
SNSでの認知度の測定方法
SNSは、ブランドの認知度を高める上で欠かせないツールです。
SNSで得られた認知を数値で可視化し、次の施策に活かすためには、適切な指標を追うことが重要です。
以下の3つの主要な指標を抑えましょう。
| 指標名 | 意味 | 測定方法 |
|---|---|---|
| インプレッション | 投稿がユーザーの画面に表示された合計回数 | 各SNSのインサイト |
| リーチ数 | 投稿を見たユーザーの数 | 各SNSのインサイト |
| フォロワー数の伸び | アカウントのフォロワー数の増減 | 各SNSのインサイト |
これらの指標を定期的に確認し、ユーザーの反応が良かった投稿やハッシュタグを分析することで、より効果的なコンテンツ戦略を立てることができます。
SNSのデータを活用して、ブランドの認知度を着実に向上させましょう。
効果測定に基づいた改善の進め方
広告やSNSでの認知施策は、一度公開したら終わりではありません。
設定したKPIを定期的に分析し、改善を続けることが成功の鍵です。
1. データに基づいた分析を行う
Google広告やSNSの分析ツールを使って、どのコンテンツが効果的だったのか、どの層に響いたのかを把握しましょう。
たとえば、「特定の広告動画の視聴完了率が低い」というデータがあれば、冒頭の数秒に改善が必要だと判断できます。
2. PDCAサイクルを回す
分析結果を基に、PDCAサイクルを回しましょう。
PDCAサイクルサイクルは以下の通りです。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 指標名 | 意味 |
| Plan(計画) | ・データから得た課題を解決するための改善策を立てる |
| Do(実行) | ・新しいクリエイティブの作成 ・ターゲット設定を調整など ・施策を実行する |
| Check(評価) | ・実行後の効果を測定し、当初の目標と比較する |
| Action(改善) | ・評価結果を基に、次の施策に活かす改善点を洗い出す |
このサイクルを繰り返すことで、施策の精度は徐々に高まり、より費用対効果の高い認知拡大が可能になります。
よくある質問
本記事では認知拡大に関するうよくある質問(以下3つ)について、回答していきます。
- 認知広告と獲得広告の違いは?
- 認知拡大の施策に予算はどれくらい必要?
- 「認知度を上げる」のにイベントは有効?
それぞれ1つずつ見ていきましょう。
認知広告と獲得広告の違いは?
マーケティング戦略を立てる上で「認知広告」と「獲得広告」の違いを理解することは非常に重要です。
この2つの広告は目的が違いますので、使い分けが必要です。
以下の表に詳細をまとめました。
| 項目 | 認知広告 | 獲得広告 |
|---|---|---|
| 目的 | ・ブランドや商品サービスの存在を広く知らせる | ・広告を見た人に購入や資料請求などの行動を促す |
| 例 | ・YouTube広告 ・SNS広告 ・テレビCM | ・ディスプレイ広告 ・メール広告 ・SNS広告 |
| メリット | ・短期間で認知向上が可能 ・話題性も期待できる | ・直接的な売上や成果に直結 ・効果測定が簡単にできる |
| デメリット | ・即効性は少ない ・即座に売上は増えない | ・長期的なブランディング効果が弱い ・リピート率を高めにくい |
この表からもわかるように、認知広告と獲得広告は役割が明確に異なります。
2つの広告を連携させることで、短期的な成果だけでなく、長期的なブランド育成にも繋がります。
広告の目的を明確にし、計画的に運用しましょう。
認知拡大の施策に予算はどれくらい必要?
認知拡大のための施策の予算は、内容や目標とする規模によって大きく異なります。
SNSの投稿やブログでの情報発信などは、広告費がかかりません。
しかし、動画制作や記事作成にかかる人件費や時間を考慮する必要があります。
また、有力でできる認知拡大の施策としては、以下のようなものがあります。
| 施策 | 費用感 |
|---|---|
| SNS・YouTube広告 | ・最低出稿金額の設定なし ・目安:1日1,000円〜数千円 ・月数万円〜 |
| TVCM | ・数十万円〜数百万 |
| オフライン広告(タクシー広告・屋外ビジョンなど) | ・数十万円〜数百万円 |
この表からわかるように、認知拡大のための予算は施策によって大きく幅があります。
手軽に始められるSNS広告から、大規模なTVCMまで、ブランドの成長段階や目的に応じて最適な施策を選ぶことが重要です。
大切なのは、単に金額をかけるだけでなく、その費用がどれだけの認知拡大に繋がったかを検証することです。
スモールスタートで効果を測定しながら、段階的に予算を増やしていくことで、費用対効果の高い認知施策を実行できます。
イベントが認知度向上に有効な理由
イベントが認知度向上に有効な理由は、主に以下の通りです。
1. リアルな体験を通じて、ブランドの価値を伝えられる
イベントでは、参加者が商品やサービスを直接手に取ったり、体験したりする機会を提供できます。
たとえば、飲食店であれば試食会、IT企業であれば新サービスのデモンストレーションなどです。
これにより、単なる情報として知るだけでなく、「体験」としてブランドを記憶に刻み込んでもらえます。
2. 口コミやSNSでの拡散が期待できる
イベントでの良い体験は、参加者による口コミやSNSでの発信に繋がりやすいです。
来場者が「#〇〇イベント」といったハッシュタグをつけて投稿することで、広告費をかけずに情報が拡散されます。
イベントに参加していない層にも広く認知を広げられます。
3. 潜在顧客と直接的な接点を持てる
イベントは、商品やサービスに少しでも興味を持っている人が集まりやすい場所です。
直接対話することで、顧客の生の声を聞き、ニーズを深く理解できます。
これは、今後のマーケティング戦略や商品開発にも活かせる貴重な機会となります。
まとめ
本記事では飲食店におすすめの認知拡大の方法をご紹介してきました。
本記事をまとめると、以下の3点です。
- 動画では料理のシズル感をアピールするのがおすすめ
- 認知拡大は感覚でなく、KPI設定をして数字で確認する
- 動画をアップしたら常にPDCAを回す意識を持つ
集客や動画制作と聞くと、難しそうに感じるかもしれません。
しかし、大切なのは完璧を目指すことではなく、まずは楽しみながらチャレンジすることです。
難しく考えすぎず、まずは動画一本からでも始めてみてください。
動画制作してみませんか?
お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。
その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。
さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!
\自社商品・サービスをさらに販売できる!/